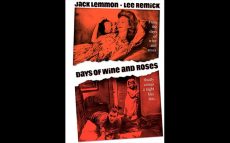【大人のMusic Calendar】
今は昔。1973年1月である。45年前「ストーンズの初来日公演」が日本政府によって中止になり、当時のファンにとってはショックであり強く記憶に残る年である。入国拒否の理由は表向き「ミック・ジャガーの麻薬に関する逮捕歴」というものだ。ストーンズは前科者で社会を混乱させるという事だったのだろう。
一方、この時期ストーンズは毎年のように精力的にニューアルバムを発表し、イギリス、ヨーロッパ、北米などでコンサート・ツアーを目まぐるしく展開していた。レコード制作は主にロンドンのオリンピック・スタジオを拠点に、ジミー・ミラーと言う敏腕プロデューサーを伴侶にして、そしてまたミック・テイラーをギタリストに迎えてから、寸暇を惜しんで楽曲制作とツアー・ライヴに明け暮れた。ミックもキースも、おそらく溢れ出る創作意欲に
かつてなく没頭したように感じられる。それは他方では、バンドの財政が破綻していたからでもあった。当時ストーンズは資金的には火の車だったのだ。その活動の全てが順調且つ円滑に進行したわけではない事が、後年になって次第に明らかになってゆく。
『山羊の頭のスープ』は発売の前年、1972年11月25日から12月21日の約1ヶ月間ジャマイカのキングストンにあるダイナミック・サウンド・スタジオで録音された。しかし、バンドのメンバー、特にミック・ジャガーはずっとキングストンに滞在したわけではない。翌年に予定された日本を含む極東アジア及びオーストラリア・ツアーの打ち合わせにロスアンジェルスに行ったり、アルバム『メインストリートのならず者』録音時に滞在した時の麻薬所持嫌疑の為にフランスのニースの裁判所に行ったりした。キースとアニタにはフランス警察から召喚状が出された事もあった。
そして、明けて1973年ハワイを含むオセアニア・ツアーを実行し、5月28日からロンドンのアイランド・スタジオで『スープ』のミキシングを行なった。この時期、キースは殆ど参加せずミックにお任せだったらしい。
このアイランド・スタジオでのミキシングこそが、むしろ重要な作業だったように思われる。後年ミックは雑誌「サーカス」のインタビューで「『メインストリート』のミキシングは気に入らない。出来ればやり直したい。だけど、『スープ』は気に入っている」と発言している。
これはミックが主導的にこのアルバムに心血を注いだからだと勝手に解釈している。それにしても、このアルバムはジャマイカで録音されながら、なぜに「レゲエぽさ」が全くないのだろう? 推考するに、ジャマイカに行ってから、楽曲を白紙から作り上げていったわけではない事は、明らかだ。歌詞の内容や曲調からして、ロンドンやニューヨーク、LAでベーシック・トラックなどをある程度仕上げてから、ジャマイカに乗り込んでいったと思われる。騒々しい外界を遮断出来るなら、どこでも良かったのかもしれない。
ただジャマイカにインスパイアされたとしたら、タイトルの『山羊の頭のスープ』。これはジャマイカに実際に伝承される料理だという。そして中に添付されたグロテスクな「山羊スープ」の写真制作は、ベロマークの考案者ジョン・パッシュのものらしい。

ミキシングを担当したアンディ・ジョーンズの記述によれば、キングストンに到着してから、最初に「アンジー」と「ウインター」を録音し(多分ストリングス・アレンジの為)、次いで「スター・スター」「カミング・ダウン・アゲイン」そしてこのアルバムに入っていないが「友を待つ」という順番で録音をしたという(これは後にアルバム『刺青の男』に収録された)。
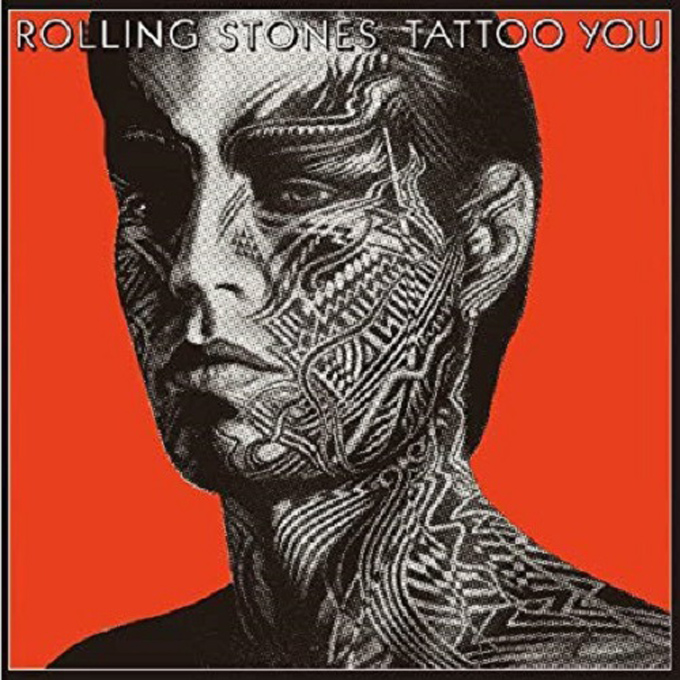
そしてこのアルバムのサウンド的特徴は、ギターよりもむしろ管楽器や鍵盤楽器の活躍である。特にビリー・プレストンの積極的な貢献は、実に素晴らしい。さらに凄いと思うのはやはりミック・テイラーである。彼の多彩で流暢で華麗なギターフレーズは、いたるところに散りばめられている。起承転結があり、ドラマチックだ。またミック・ジャガーの充実した歌唱も一段と多彩で素晴らしい。
当時、世情ではグラムロック、すなわちT・REXやデビッド・ボウイなどが急成長していた。また、レゲエが破竹の勢いで巷間に広まっていた。これをミックが見逃す事はないだろうと思った。だがこのアルバムにはその影響は殆どない。むしろサウンド的にファンクやソウルの片鱗が伺える所が面白い。レゲエの影響は、その後のストーンズのアルバムに少しずつ聴かれるようになっていった。ただ視覚的なグラムロックの影響は、4本のプロモ映像に如実に表現されている。「アンジー(2ヴァージョン)」「シルヴァー・トレイン」「ダンシング・ウィズ・ミスターD」。これらは7月24日、25日にロンドンにて撮影された。ミック・ジャガー30歳である。
当時、日本では六本木にあった「ワーナー・パイオニア」がディストリビュートしていたのだが、販売担当の庭野課長が「アンジー/シルヴァー・トレイン」のシングル盤発売日(8/20)直後「いやあ、池田君、御陰様で大ヒットだよ。素晴らしい! ありがとう」と言ったのを昨日の事のように思い出す。それで「どのくらい売れたんですか?」と聞くと「そうだね、今の所、13万枚くらいかな」と答えた。内心、「な〜んだ。100万枚とかじゃないんだ」と日本の洋楽の市場規模を初めて感じた瞬間だった。
この後で知ったのだが、ストーンズのアルバム・セールスは、当時10万枚を越す事は珍しかったらしい。
このアルバムは、英米のヒットチャートで1位となり、英米のファンの間では評価が高い。しかしながら、ここ日本においては「掴み所がない」「散漫な印象」「地味な感じ」などネガティヴな評価が見受けられる。それはこのアルバムのコンセプトが見えにくく、つまり自虐的でコミカルな英国流のストーンズ・ファンタジーが見えないからだと思われる。それが日本的感性になじまないのだと思う。例えば1曲目のマイナーペンタトニックスケールを単純になぞったような幻惑的なリフで始まる「ダンシング・ウィズ・ミスターD」の意表を突いた詩的世界は、かなり実験的でモダンなブルースだと思う。キースは「このアルバムは、ある種の冒険だった」と語っている。その意味はおそらく「ファンの期待する音楽」ではなく「新境地の開拓」ではなかっただろうか。ストーンズの音楽は常に古くて新しく、単純にして複雑なのである。
冒頭で記述した来日中止の怨みもあって、1973年9月、僕たちは50人のツアーを組んで決死の覚悟でロンドンまでストーンズを観に行った。ロンドン公演ではこのアルバムから「ダンシング・ウィズ・ミスターD」「スター・スター」「アンジー」「シルヴァー・トレイン」「ドゥー・ドゥー・ドゥー(ハートブレイカー)」を演奏した。他の所では「100年前」をも演奏したらしい。
日本ではシングル盤の「アンジー/シルヴァー・トレイン」しか発売されていなかったので、他の3曲はライヴで初めて聴いたのだった。それは新鮮な感動でもあった。ライヴの「アンジー」はエレキで演奏し、荒々しく、レコードの印象とはまったく異質の曲で驚いた。そして、そのド迫力の演奏にストーンズの「ライヴ至上主義」みたいなものを直感した。
話は現在に飛ぶが、昨年、No Filter Tourでドイツに行った時に、突如「ダンシング・ウィズ・ミスターD」が飛び出した。その瞬間、僕は45年前にぶっとんでいた。
【著者】池田祐司(いけだ・ゆうじ):1953年2月10日生まれ。北海道出身。1973年日本公演中止により、9月ロンドンのウエンブリー・アリーナでストーンズ公演を初体感。ファンクラブ活動に参加。爾来273回の公演を体験。一方、漁業経営に従事し数年前退職後、文筆業に転職 。