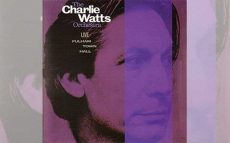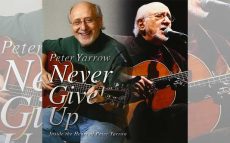ある人は、『シルク・ディグリーズ』のお洒落なジャケットを手に、AORの代表的な存在としてのボズ・スキャッグスについて、その魅力を説く。いや、マッスル・ショールズ録音のアトランティック盤(『ボズ・スキャッグス』)こそが一番だと譲らず、デュエイン・オールマンの快演とともにブルース談義に花を咲かせる人もいる。人によっては、『マイ・タイム』の頃の、サンフランシスコの夕暮れに映える彼の歌声やギターを真っ先に思い浮かべるかもしれない。
こうやって、ボズ・スキャッグスに対する思いは、人によってそれぞれだ。ぼくのような優柔不断な人間は、どれもボズ・スキャッグスなんだよなあ、と当たり前のことを思い、甘い歌声ももちろんだが、ギターだって捨て難いと、ぶつぶつ呟きながら、その日の気分によっていろいろとアルバムを引っ張り出してくる。
近年だと、やはり、『メンフィス』。例のメンフィス録音、それも、ロイヤル・レコーディング・スタジオでの録音による傑作だ。往年のハイ・サウンズを再現するような、心地のいいリズムに酔いながら、一度しか行ったことのないのに、メンフィスのビール・ストリートに思いを馳せたりもする。
実際、彼も、アル・グリーンやアン・ピーブルズのレコードで慣れ親しんだウィリー・ミッチェルによるハイ・サウンズが、スタジオの隅々に沁み込んでいるのを感じたという。だからこそ、テクノロジーの進化で似たような音が作れるようになったにもかからわず、時代に逆らうようにわざわざメンフィスにまで足を運んだ。
もちろん、その内容も素晴らしいが、チャールズ・ホッジズやスプーナー・オールダムのようにメンフィス所縁の人たちに交じって、その『メンフィス』で、ベン・コーリーの名前を見たとき、ぼくは、嬉しくて震えるくらいだった。メンフィスの名門バーケイズのトランペット奏者だが、1967年、オーティス・レディングの飛行機事故で生き残った人でもあり、スキャッグスのアトランティック盤の幕開けを飾る「アイム・イージー」で、トランペットを吹いていた人でもあったからだ。
こういうところが、音楽に物語を寄り添わせてくれるというか、スキャッグスらしいな、と思うが、ちなみに、コーリーは、続く『ア・フール・トゥ・ケア』にも参加している。しかし、2015年9月、67才で鬼籍に入る。その『ア・フール・トゥ・ケア』と、キース・リチャーズの『クロスアイド・ハート』が、彼のトランペットが聴ける最後のアルバムとなった。
ともあれ、6月8日は、ボズ・スキャッグスの誕生日らしい。1944年生まれだから、73才になる。そうか、彼もそういう年齢になったのかと、しみじみとしながら思い出されるのは、1976年の暮れ、オークランドのパラマウント・シアターで観たコンサートだ。
米国有数のアール・デコの建造物として知られるこの劇場で、彼は、1974年からビル・グレアムの提案でブラックタイ・コンサートを行なっていた。殊に、1976年は、『シルク・ディグリーズ』の成功もあったし、カリフォルニアに滞在中だったぼくは、友人と一緒に勢い込んで会場に足を運んだ。
ブラックタイにロングドレスという男女で会場は埋まっていた。レス・デュデックやジェフ・ポーカロといったメンバーを率いるボズ・スキャッグスも、タキシード姿で、曲によっては優雅にストリングスをバックに歌い、演奏した。ぼくらは、ジーンズにセーターの普段着だ。場違いなところに紛れ込んだようで、友人と顔を見合わせ、苦笑いしながら、それでも、素晴らしい歌と演奏に酔った。
そして、こういうロックの楽しみ方もあるんだなあ、ひょっとすると、ぼくらは、少なくともぼくは、ロックとはこういうものだと、気づかないうちに作り上げていたところもあるのかもしれないなあ、そんなことを思いながら帰路に就いた。
日本と米国との文化の違いもあるだろうけれど、聴き手であるぼくらはもちろん、ミュージシャンも年齢を重ね、それ以上は信じるなと言われた30才(彼は既にその年齢を超えていた)が間近に迫っていた。ロックと共に10代、20代をすごしてきたぼくらは、どうやって、それまでとは違う大人になり、ロックとかかわり、時代と向き合っていけばいいのだろうか。漠然とだが、そんなことを考えさせられたコンサートでもあった。
それから、いつの間にか40年だ。その彼も、73才になり、いまさらの感もあるが、果たしてぼくはどんな大人になったのだろうかと、我が身に問いかけたりもする。
【執筆者】天辰保文(あまたつ・やすふみ):音楽評論家。音楽雑誌の編集を経て、ロックを中心に評論活動を行っている。北海道新聞、毎日新聞他、雑誌、webマガジン等々に寄稿、著書に『ゴールド・ラッシュのあとで』、『音が聞こえる』、『スーパースターの時代』等がある。