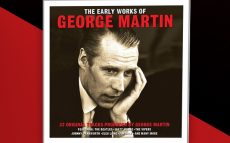武蔵野タンポポ団 ― 伝説の向う側
公開: 更新:
【大人のMusic Calendar】
1972年の今日、1月10日はアルバム『武蔵野タンポポ団の伝説』がリリースされた日である。
私がこの原稿を書くことについては、タンポポ団の中核、シバ君には申し訳なく感じる。だいたい私はメインボーカルも取らず、楽器もギロ(へちまみたいな格好をした木製の円筒をワリバシみたいな木の棒でギロギロとこすって音を出す打楽器)やカズー担当で、いてもいなくてもいいようなもの。とても中心メンバーとは言い難い男だった。だから、今回の私の役割としては、この摩訶不思議なバンドのオリジナルメンバーでいながら、どっぷりとはまり込んではいない、テキトーな立場であったのを良いことに、タンポポ団について少し客観的にお伝えすることかなと考える次第。おつきあいよろしく。
1971年の初夏、場所は東京の吉祥寺。そこにぐゎらん堂という店があった。そのぐゎらん堂のビルの屋上で、私はかの高田渡(以後渡と表記)、シバ、若林純夫、村瀬雅美といった面々とギターを弾いていた。タンポポ団のスタートである。私は若林に声をかけられてこのグループに参加した。渡はというと、彼はこのバンドで夏にある第三回中津川フォークジャンボリーに出演することを考えていた。目標があればメンバーの士気は高まる。その上、結成ホヤホヤのバンドが演奏する場所は屋上から階段を少し降りれば、フォーク喫茶+酒場のぐゎらん堂がある。そこでお客さん達の反応を見ながらステージを重ねていけば間違いはない。
そして、夏が来た。中津川の熱気はこの年も高まっていた。その中でも去年より声高に感じられたのが「帰れコール」だった。ステージ上の歌手に金を払って観に来た聴衆が「帰れっ!」と叫ぶのだからもったいない話だが、当時のフォークファン、特にいわゆる関西フォークのファンの多くは、歌い手と聞き手という線の引き方をしていなかったように思う。彼らにとってみれば、自分たちの代表がフォーク歌手であり、仲間の延長なのだ。だから、ポップな、仲間とは思えない歌手が登場すると、「帰れっ!」となる。
さて、いよいよタンポポ団の出番、どうなるんだろう? なんせ全く無名の存在なのだから。
結果は、大いにウケた。そりゃ渡の他に加川良も登場し、岩井宏や中川イサトがセッションに加わったわけだからウケないはずがない。どころか、中津川以降、噂がウワサを呼んで、あちこちから声がかかった。多くの場合、渡の出演するコンサートに金魚のフンの如くメンバーがくっついて行って、ついでにタンポポ団として出演するパターンだったが、ちゃんとコンサート出演者に名を連ねていた。
そうしたタンポポ団が、なぜ「伝説」と呼ばれるようになったのだろう。一つは、バンドに聴衆が求めるものの大きな要素、本物の“仲の良さ”があったからだろう。実際メンバーの殆どが吉祥寺に暮らし、ぐゎらん堂をたまり場として、日々近くの店を飲み歩く。ステージでも和気合々、曲間のおしゃべりも掛け合い漫才のようだった。その暖かさの中に、意外な飛び入りメンバーが入ってくる。そのワクワク感もたまらない。もう一つは、曲がシンプルなこと。難しいコードも無く、リズム上の仕掛けもない。ギターのスリーコードさえ弾ければ誰でもが参加できそうだ。まさに聴衆にとってはステージの高さを感じない、仲間的な歌手とのひとときを楽しめるのだ。そして、その歌の内容は自分たちの暮しや思いをしっかりと言葉にしてくれている。奥が深い。こうした温もり感が一層プロ化していこうとするフォークの流れと逆行するように、フォークの源流を知る、共に歌いたい若者たちを惹きつけていったに違いない。
ステージのあと、当日払いの、決して多くはないギャラをポケットに入れると、そのままメンバー皆で飲みに行った。飲めない若林と私を除いてとことん酔う渡やシバたち。思えば一日の過ごし方としてこんな素敵な世界はなかった。そこに歌があって、仲間みんなで心底それを楽しんだ。そんな姿が武蔵野タンポポ団だったのです。
【著者】山本コウタロー(やまもと・こうたろう):1948年、東京都千代田区生まれ。一橋大学在学時に「走れコウタロー」が大ヒットし、日本レコード大賞・新人賞を受賞。その4年後「岬めぐり」がヒット。地球環境問題、平和問題、男女共同参画などに造詣が深く、白鴎大学教授を務める。