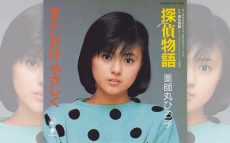【大人のMusic Calendar】
東京五輪・パラリンピックが開催される2020年完了を目途に、“百年に一度”とまで言われている渋谷駅周辺の大規模な再開発が進んでいる。2012年4月、東急文化会館の跡地に建設された「渋谷ヒカリエ」のオープン、翌2013年3月に東急東横線渋谷駅の地下化などから始まったことでも明らかなように、この渋谷駅周辺再開発プロジェクトを推進している中心的存在は東急グループである。
戦後、空襲の焼け跡に立った闇市からスタートした渋谷の復興・開発の主導権を握っていたのも東急グループの母体である東急電鉄で、東急文化会館(57年)、渋谷東急プラザ(65年)、東急百貨店本店(67年)等を次々とオープン。渋谷は“東急の街”として発展していったのである。そんな東急の“シマ”に斬り込んでいったのが、池袋・新宿を拠点としていた西武流通グループで、東急百貨店開店の翌年1968年4月に西武百貨店渋谷店をオープン。これが西武の渋谷進出の第一歩となった。
現在の姿からは想像つかないだろうが、当時の渋谷には映画館やジャズ喫茶以外に若い世代を引き寄せるような店が乏しく、現在の「109」の裏手「プライム」あたりにあった「緑屋」というショッピングビルが、唯一“おしゃれ”と呼べるような場所であった。しかし、その近辺には戦後闇市の名残のような一角もまだ残っており、当時の若者が好む繁華街ランキングでは、トップの新宿をはじめ、銀座、赤坂などに大きく水をあけられていたのだ。
そんな渋谷に出店するにあたって、西武百貨店が打ち出したコンセプトが若年層の取り込みで、渋谷を“若者の街”化することであった。その宣伝戦略の第一弾となったのが、西武百貨店渋谷店のキャンペーン・ソング(現在で言うならばイメージ・ソング)の制作で、歌詞を公募し当選作を歌手に歌わせレコード化するというものだった。
歌い手として起用されたのはザ・ワイルドワンズ。GSブームの真っ只中でGSをめぐる様々なトラブルが社会問題にもなっていた当時、デビュー2年目を迎えても学生バンドのような清廉なイメージを失っていないことが、抜擢の大きな理由と思われる。
月刊誌『平凡』誌上で歌詞が一般公募され、大阪在住の主婦・島田陽子(同名女優とは別人)さんの応募作品「恋のヤング・タウン」が当選。これに作詞家の山上路夫が手を加え、加瀬邦彦が作曲して完成したのが「花のヤング・タウン」で、「バラの恋人」に続くザ・ワイルドワンズの通算7作目のシングルとして、今から50年前の今日1968年7月10日にリリースされた。

リード・ヴォーカルは植田芳暁。レコードで聴くと、彼の叩くドラムの音がいつもと違ったデッドな響きでオン気味に聴こえるのが印象的だが、これは当時東芝レコードのハウス・エンジニアだった吉野金次がビートルズの録音方法を研究して試行錯誤した結果らしい。全体的なミックスのバランス、音の抜けの良さも同時代のGS作品とは一線を画しており、後年の彼の活躍を予期させる出来栄えである。
デパートのキャンペーン・ソングがヒットした前例としては、フランク永井の「有楽町で逢いましょう」(有楽町そごうのキャンペーン・ソング)があるが、「花のヤング・タウン」はそこまでの大ヒットには至らなかったものの、約8万枚のセールスを記録し、オリコン最高位18位にランクされた。そして、西武百貨店を渋谷進出の足掛かりとした西武流通グループは、70年代に入り渋谷PARCOをオープン。公園通りを整備し、やがて“シブヤ系”に代表される世界に名だたる若者文化発信拠点の街へと渋谷を大変貌させるのである。

ザ・ワイルドワンズ「花のヤング・タウン」フランク永井「有楽町で逢いましょう」写真撮影協力:鈴木啓之&中村俊夫
【著者】中村俊夫(なかむら・としお):1954年東京都生まれ。音楽企画制作者/音楽著述家。駒澤大学経営学部卒。音楽雑誌編集者、レコード・ディレクターを経て、90年代からGS、日本ロック、昭和歌謡等のCD復刻制作監修を多数手がける。共著に『みんなGSが好きだった』(主婦と生活社)、『ミカのチャンス・ミーティング』(宝島社)、『日本ロック大系』(白夜書房)、『歌謡曲だよ、人生は』(シンコー・ミュージック)など。最新著は『エッジィな男 ムッシュかまやつ』(リットーミュージック)。