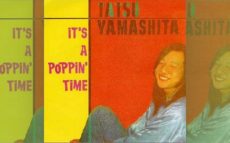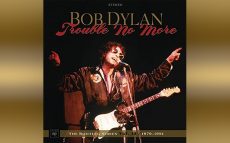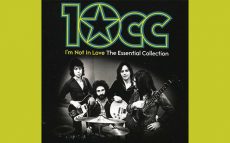【大人のMusic Calendar】
70年代前半の日本ロック・シーンに突如として登場し、革ジャンにリーゼント、クールなオリジナル・ロックンロールで一世を風靡した伝説のキャロル。矢沢永吉とジョニー大倉という強烈な個性と才能溢れるフロントメンを擁したこのバンドに於いて、その二人より半歩下がったような立ち位置で黙々とギターを弾きながらも、決して埋没することなく独自のオーラを放っていたのがキャロル“第三の男”ウッチャンこと内海利勝だった。本日5月30日は、彼の65歳の誕生日である。
1953年5月30日、神奈川県鎌倉市出身の内海利勝は、高校時代からエリック・クラプトンに憧れギターをはじめ、もっぱらクリームやブルース・ロックを演奏していたという。関東学院大学に進学後セミプロ・バンドで活動。ある日楽器店で見つけたメンバー募集の貼り紙がきっかけとなり、矢沢永吉、ジョニー大倉たちとキャロルを結成する。
横浜・伊勢佐木町のディスコ『ピーナッツ』でステージ・デビュー後、横浜・川崎・蒲田といった京浜地区のキャバレーやディスコのハウス・バンド(所謂“ハコバン”)として活動を続けていたキャロルだが、72年10月にTV 『リブ・ヤング!』(フジテレビ系)に生出演したところをミッキー・カーチスに見出され、同年12月、ジョニー(作詞)と矢沢(作曲)によるオリジナル作品「ルイジアンナ」でレコード・デビューした。

長髪のヒッピー風スタイルのバンドが主流だった当時のロック・シーンに、ハンブルグ時代のビートルズのような風体で、オールド・ロックンロールとマージー・ビートをミックスしたようなオリジナルを演奏するキャロルの登場は、衝撃を持って迎えられ、ロックとは無縁だったローティーン、ヤンキー、そして文化人たちまでに至る幅広い支持を集め、社会現象にまでなっていった。
矢沢とジョニーの強力なコンビと寡黙な内海のコントラストは、ビートルズにおけるジョン&ポールとジョージの対比に似たものを感じるが、ビートルズ時代のジョージ・ハリスンが、レノン&マッカートニー作品にメロディアスでキャッチーなギター・フレーズをイントロや間奏、オブリガードで提供していたように、内海もまた楽曲の一部として計算された“歌えるギター・フレーズ”の名手であり、キャロル作品にさらにキャッチーな彩りを添える重要な働きを担っていた。その最高傑作ともいえるのが「ファンキー・モンキー・ベイビー」のイントロだろう。作曲者クレジットに彼の名を加えても良いほどだ。

75年4月13 日の日比谷野音でのコンサートを最後にキャロルは解散。ジョニー、矢沢に続いて、内海も同年10月にシングル「鏡の中の俺」でソロ・デビューし、翌月には英国のレゲエ・グループ「シマロンズ」との共演アルバム『GEMINI part 1』を発表して話題を呼んだ。キャロルの幻影を振り払うかのように、レゲエというまるで別のアプローチで音作りを始めたところなども、どこかジョージとダブるものを感じてしまう。

その後、紆余曲折のソロ活動を重ねコンスタントにアルバムをリリース。現在は、アコースティック・ブルースを基本とした独自のヴォーカル&ギター・スタイルを確立しマイペースな音楽活動を展開しているが、ここに辿り着くまでの道のりは決して平坦なものではなかったようだ。解散後30年以上経っても“元キャロルのウッチャン”を望むリスナーとの葛藤にも苦しんだという。伝説のキャロルの残像と幻影は、メンバー本人が思いもよらぬほど大きなものだったのである。
【著者】中村俊夫(なかむら・としお):1954年東京都生まれ。音楽企画制作者/音楽著述家。駒澤大学経営学部卒。音楽雑誌編集者、レコード・ディレクターを経て、90年代からGS、日本ロック、昭和歌謡等のCD復刻制作監修を多数手がける。共著に『みんなGSが好きだった』(主婦と生活社)、『ミカのチャンス・ミーティング』(宝島社)、『日本ロック大系』(白夜書房)、『歌謡曲だよ、人生は』(シンコー・ミュージック)など。最新著は『エッジィな男 ムッシュかまやつ』(リットーミュージック)。