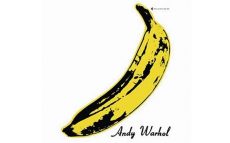【大人のMusic Calendar】

本日7月26日はこの3月に惜しくも亡くなった萩原健一の誕生日である。
80年代の『月刊宝島』で萩原健一・ショーケンは2度表紙を飾っている。最初にインタビューしたのは82年春、ロッカー・ショーケンの名が輝きを増していく頃だった。

テンプターズ、PYGを経てから、70年代は役者としてブレイク。『傷だらけの天使』『前略おふくろ様』などテレビシリーズの主演で圧倒的な人気を確立し、中盤からは、柳ジョージとレイニーウッドを従え、グループサウンズのアイドルスター色を完全に脱却し、正面からブルース色の強いロック・バンドサウンドへ挑み、ミュージックマガジン誌でも年間ベストアルバムに『熱狂雷舞』(1979年)が選ばれた。
当時は桜井さんというショーケンと長らく付き合ってきた方がマネージメントをされていて、「やんちゃですからね、うまく行けばいいですけど、まあ宝島ならだいじょうぶでしょう。週刊誌じゃないから。あ、ショーケンとは呼ばないでください。怒りますから」と事前に不安を煽るご注意をいただいた。
指定された場所は、今はない赤坂TBS会館の「ざくろ」。高級しゃぶしゃぶ料理店で、当時の編集費からは考えられない場所だった。
インタビュアーは加藤芳一君で、TVプロデューサーとして高名な高平哲郎氏の弟子にあたる放送作家の駆け出しで、当時よくタッグを組んでいた。私もともにまだ30歳にもなっていないひよっこチームだ。
インタビューは、周囲が心配するほど口数の少なく、じゃっかん吃音調の、いつも通りの加藤ペースで始まる。「あーの、ハ、ハギワラさんは埼玉、オ、オオミヤですか?」
しばらくして、スローペースが気に障ったのか、ショーケンが「あのさあ、あなたがた、いい大学出てるんでしょ。もっとマシなことできないの? 俺、帰るわ!」
長い編集者人生で、あとにも先にも、ここまでのピンチはなかった。空いたページはどうする? ここの勘定、会社に清算できるのか? ダメなら確実に給料の大半が飛ぶ! どう謝ったか覚えてないが、立ち上がったショーケンを2人でなんとか席に戻し、その後は無事に終了。テンプターズからPYG、そしてレイニーウッドへの音楽の流れを気持ちよく語ってもらった、と思う。
その2年後も、同じチームでショーケンのインタビュー・撮影を行なった。このときはカメラは吉田ルイ子氏。相変わらず低姿勢なポンコツ二人組はなぜかすっかり気に入られて、「おお、また宝島来たね」と言った笑顔が忘れられない。加藤君はショーケンとその後、連れションをしたことまで書き残した。また新婚だった当時の私には、「結婚? 錯覚だからねー。気をつけな。まあハメればすべてなんとかなる!」と、ほとんどインタビューにならないパイセン話が炸裂した。

役者としては別として、ロッカー・ショーケンの全盛期は意外と短かったかもしれない。1984年、マリファナで逮捕された保釈後の読売ランドイーストでの復帰コンサート。タバコを客席にばらまき、「悪いことやってんじゃねーか?」と不敵なMCで幕が開き、「アイ ラブ ボァブ・ディラーン! ボァブ・マーレー!」と連呼し、語るような歌声と凄まじい集中力で客を完全にショーケンワールドに連れて行ってくれた。ある面、実は「演じる役者の音楽」だったのかもしれないが、ただ、だからこそ出る引力がある。原田芳雄、松田優作なども素晴しいロックを残している。
加藤芳一君は、その後テレビ界で活躍し、「冗談画報」「ごちそうさま」「ポンキッキーズ」「タモリ倶楽部」などで名を上げたが、これからという時、42歳で他界した。
「久振りです。ハ、ハギワラさん」「おう宝島っ!」天で会話しているはずだ。
月刊宝島1982年7月号、月刊宝島1984年5月号 表紙写真提供:関川誠
【著者】関川誠(せきがわ・まこと):「株式会社宝島社取締役雑誌局長」。80年代から90年代、伝説となった雑誌「宝島」の編集長を務める。その宝島で80年代に萩原健一の取材を2度行った。