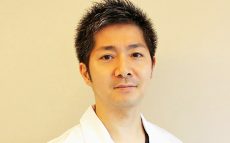それぞれの朝は、それぞれの物語を連れてやってきます。

中川雅哉さん
大きな団地が建ち並ぶ東京のベッドタウン、千葉市稲毛区に1軒のお店があります。
名前は「ぷりんと工房・小仲台店」。ひと昔前はよくあった、フィルムの写真を現像してくれる「DPE」のお店です。でも、一歩店に足を踏み入れると、フィルムカメラが約700台も並んでいます。
店長の中川雅哉さんは、1962年生まれ。小学5年生の誕生日にコダック・インスタマチックを買ってもらったのがきっかけで、写真の世界にどっぷり浸かります。中学・高校はもちろん写真部。家には収集したカメラを湿気から守る倉庫もつくりました。
中川さんは、縁あって大手スーパー・西友のカメラコーナーを運営する会社に入ります。38年前・1985年の日本シリーズにおいて、タイガースがライオンズを破って日本一に輝いた際は、当時の西友はセゾングループだったにもかかわらず、派手に六甲おろしをかけてタイガース優勝セールを開催するなど、ユニークなお店づくりで営業も絶好調でした。

「ぷりんと工房・小仲台店」
しかし、転勤とお父様の介護が重なった中川さんは、やむなく会社を辞めます。1999年、自宅近くに現在の写真プリント店を開店しました。当時、稲毛の団地は子育て中の家族が多く、次から次にフィルムが持ち込まれました。従業員も5人ほど雇って、お店は大盛況だったそうです。
しかし、程なくして手ごろなデジタルカメラや高機能プリンターの人気が沸騰。お店に持ち込まれるフィルムも、あっという間に少なくなっていきました。「これからどうしよう」と悩んでいた矢先、中川さんの家を訪ねてきた古くからの友人が、ズラッと並んだコレクションのレトロなカメラを見て、こんなことを言ったそうです。
「古物商の免許を取ったらどう? 古いフィルムカメラが欲しい人もきっといると思うよ」
2005年、中川さんはフィルムカメラ専門店へのシフトを決意しました。

価格が高騰するフィルム
新たなスタートを切った中川さん。最初はデジタルカメラの普及でお役御免となった、フィルムカメラの買取りで盛況となりました。それもすぐに落ち着くと、店を訪れるのはご近所の中高年の写真愛好家ばかり。1ヵ月に売れるカメラも、せいぜい4~5台程度の日々が続きます。
ところが、2010年代に入ってしばらくすると、店に異変が起こりました。なぜか大学生くらいの若い女性が2~3人で訪れることが増えたのです。
驚いた中川さんは、女の子たちにどうしてお店に来てくれたのか尋ねてみました。すると、スマートフォンを見せつつ「SNSで紙焼きの写真があるのを知ったんです」と教えてくれたそうです。
さっそく中川さんは、昭和40年代につくられた金属むき出し・銀色ボディのフィルムカメラを手に取り、冷たい手ざわりを感じてもらいます。さらにフィルムも入れ、「ギリギリ、ギリギリ」と巻き上げレバーでフィルムを巻いてもらいました。
「なにコレ、エモーい!!」
スマホでしか写真を撮った経験がなかった女の子たちは、目を丸くして大感激したそうです。いわゆるレトロブームの到来を、中川さんは肌で実感することになります。

人気の金属ボディのフィルムカメラ
そんな彼女たちは、やがて彼氏や家族を連れてお店に来るようになりました。さらに、中川さんがフィルムカメラの情報を店のSNSで発信すると、全国からやって来る人も増えていきます。いつしか中川さんの店には、若い人の声が溢れるようになっていきました。
そんなレトロブームに水を差したのが、2020年からのコロナ禍です。外出が減ったことで写真を撮る人も減り、カメラもフィルムも売れなくなりました。これに原油高、円安、ウクライナ戦争が追い打ちをかけ、36枚撮りフィルムは5年間でほぼ3倍に値上がりし、1本1500円を超えました。
中川さんは、この現状に危機感を覚えます。せっかくフィルムカメラの面白さに気付いてくれた若い世代が、生活でいっぱいいっぱいになってしまい、趣味にお金を使う余裕がない……そんな時代の空気を感じるからです。でも、中川さんは諦めていません。
「フィルムカメラで撮れる写真は一期一会なんです。カメラはもちろん、レンズやフィルムの材質が違えば、1枚として同じ写真はありません。その世界をもっと多くの方に楽しんで欲しいんです」
2023年11月1日に61歳の誕生日を迎えた中川雅哉さん。フィルムカメラと紙焼き写真の「文化」を次の時代につなぎたいという思いを胸に、力強く語ってくれました。
「体が続く限り、お店は続けます!」