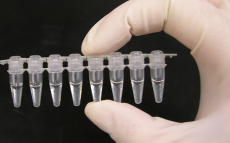北朝鮮拉致問題に本気で取り組んで来なかった日本~その歴史的な背景
公開: 更新:
ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」(6月8日放送)にジャーナリストの須田慎一郎が出演。横田滋さんが亡くなった報道を受け、北朝鮮による拉致問題について解説した。
横田めぐみさんの父、滋さん死去
1977年に北朝鮮に拉致された横田めぐみさん(拉致当時13歳)の父・横田滋さんが5日、老衰のため87歳で亡くなった。被害者家族の象徴的な存在で、長年にわたり拉致問題の解決を訴え続けて来たが、願いは叶わなかった。
飯田)体調が思わしくないということも伝えられていましたけれども、無念でしょうね。
政権、国民は本気になって拉致問題に取り組んで来たか
須田)横田めぐみさんは1977年に拉致されたということなのですけれども、以後20数年間、放置されていました。ようやく動いたのが2002年です。小泉政権時代に初の日朝首脳会談が行われ、結果的に拉致被害者のうち何人かが帰国することになった。当時の北朝鮮を取り巻く国際環境を考えると、アメリカによる体制転覆、北朝鮮に対する攻撃のリスクが高まっていた。それに対して、直接交渉ルートがなかった北朝鮮が日本を頼って来た。そういう側面があり前進したのに、そこで留まってしまった。いまは米朝間で直接の対話ルートができてしまい、日本が登場する場面がないということで、足踏みしている状況です。とはいえ、日朝平壌宣言はまだ有効とされている状況のなかで、果たして政権や国民も含めて、本気になって取り組んで来たのかというと、忸怩たる思いがあります。
飯田)あのとき、拉致被害者の5人の方々が帰って来たけれど、一時滞在して戻すというはずだった。でもそんなことをしたら、日本の世論がどうなるのか。官邸でも中山恭子さんや、当時副長官であった安倍晋三さんが反対をしたというのもあったとは思いますが、世論が北朝鮮に返すなんてとんでもないと高まった。むしろ5人が帰って来たところで、「やはり拉致があったではないか」と世論が沸騰した。あのうねりを北朝鮮側が恐れる部分があるのでしょうか?
須田)世論の部分と、もう1つは、北朝鮮の核ミサイルの問題を解決するために、6ヵ国協議の枠組みをつくったわけですよね。日本はそこに入るべきなのでしょうけれども、これが何だったのかというと、北朝鮮に対する経済支援・援助ということが当然出て来ます。それを担うのは日本であり、韓国という状況だった。経済支援援助ということも含めて、日本のカードはないわけではない。しかし、それを利用して来なかったというところも1つある。
拉致問題を放置し続けた政治的背景
須田)一方で、金丸脱税事件というものがありました。自民党の中心である副総裁の脱税事件が起こって、事務所の金庫のなかから無刻印の金塊が出て来た。当時、「無刻印の金塊は北朝鮮から提供されたもの以外にない」と言われていた。金丸訪朝団が行ったときに貰ったのではないかと言われました。また当時、社会党幹部の土井たか子さんが「拉致はない」と言った。そういう国内の政治状況が、この問題を放置し続けたという事実があります。それに対する反省がきちんと行われたのかどうかというところもあります。
飯田)辛坊治郎さんが、当時は拉致のドキュメンタリーをつくろうとしても、「北朝鮮がそんなことをするわけがないだろう」と、「米帝のプロパガンダを許すな」と言われて、ドキュメンタリーを地方局はつくれなかったということを、実体験として語っていました。当時はそういうメディア環境という面もあったのですよね。
須田)そうですね。拉致の問題以前に、北朝鮮批判をやると朝鮮総連から相当なクレームが来る。加えて当時の社会党が朝鮮総連と密接に結びついていた。そちらからもクレームが来るということで、拉致問題を真正面から取り上げられない。拉致問題だけではなく、北朝鮮に対する批判について、日本のメディア環境としては、きちんと報道できなかった。唯一、報道したのは、産経新聞くらいではないでしょうか。
飯田)産経新聞も新潟支局発で大展開をしたときに、「世紀の大誤報だ」とされて叩かれました。あのときに批判していた人は、何か落とし前をつけたのかというと、何もやっていないですよね。