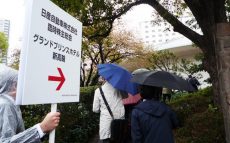決算発表後にみせたトヨタと日産の動き…そのDNAは?
公開: 更新:
「報道部畑中デスクの独り言」(第131回)では、ニッポン放送報道部畑中デスクが、トヨタ・日産がそれぞれ掲げた新技術について解説する。

日産・横浜本社8階の新技術説明会 会場は2日前の決算発表と同じ場所だった(5月16日撮影)
先週、厳しい決算が明らかになった日産自動車ですが、その2日後、新技術の説明会が決算発表と全く同じ場所で開かれました。その技術とは将来の自動運転につながる運転支援技術「プロパイロット」の進化版でした。
「プロパイロット2.0は人工知能の採用状況からいっても世界最高レベルの技術だ。簡単にこれを超えて次のステップに行くということはできない。いまできるすべての技術を投入し、最もドライバーに安全で使いやすいシステム」
技術開発担当の飯島徹也部長はこのように語り、自信を見せました。
今回のシステムは高精度の3次元地図データなどを活用することで、カーナビゲーションと連動して運転を支援するのが大きな特徴です。高速道路の同一車線、さらにドライバーが状況に応じて、ただちにハンドルを確実に操作できる状態であることを条件とした「手放し運転」を可能にするものです。

記者会見する中畔邦雄副社長
自動運転のレベルで日産は「レベル2とレベル3の間」と説明します(レベル2は「システムがステアリング操作、加減速のどちらもサポート」、レベル3は「特定の場所でシステムがすべてを操作、緊急時はドライバーが操作」を意味する)。
また、追い越しも車両が自動的に行う仕掛けがあります。前方の車の速度が遅いとき、システムが「追い越し可能」と判断すると、車内の表示や音で提案します。ドライバーが追い越したい場合は、ハンドルに手を添えながら、スイッチで承認すると自動で車線を変更します。この“世界初”のシステムは今年(2019年)の秋に、日本で発売される予定の「スカイライン」に搭載されるということです。
このシステムは前述の地図データやトライカムと呼ばれる「3つの目」をもつカメラがキーデバイスになっていますが、地図はゼンリン、カメラの心臓部はモービルアイというイスラエルの企業の技術が採用されています。

プロパイロット2.0のシミュレーション画像
「先進的な技術を詰め込んだ形でクルマとしてのパフォーマンスの高いものを出し続ける会社。そういうパワーを持ち続けることが非常に大事なことと思っている」
2日前の決算会見での西川広人社長の発言です。発言について前回の小欄では厳しい指摘をしましたが、日産がこういう会社であるべきという姿勢については理解できます。説明会では、技術スタッフの1人が「会社がどういう状況でも、技術陣のマインドは変わっていない。お客様にいいクルマを届けるかどうかだ」と話していました。この思いは持ち続けてほしいものです。

東京・江東区のトヨタのショールーム「MEGA WEB」で発表イベントが行われた モニターに映っているのが友山茂樹副社長(5月17日撮影)
一方、トヨタ自動車は先の決算会見の翌日にパナソニックと住宅事業での提携強化を打ち出しましたが、先週は「新型スープラ」の発売を開始しました。スープラは言わずと知れたトヨタ往年のスポーツカー、日本では当初、セリカの上級仕様「セリカXX(ダブルエックス)」として登場しましたが、輸出名は「スープラ」、その後、日本でもスープラに統一されます。今回で5代目となりますが、2002年に排出ガス規制の影響で消滅して以来、17年ぶりの復活となりました。

17年ぶりの復活となった新型スープラ
「SUPRA IS BACK」
東京都内で開かれた発表イベントでは、このようなコピーが躍りました。友山茂樹副社長は次のように語ります。
「クルマ好きがだんだん世の中にいなくなったと言うが、決して若い人がクルマから離れて行ったわけではなくて、我々メーカーの方から楽しいクルマ、いいクルマをつくることを忘れていたのではないか。原点に返りたいと思いが込められている」
「社長の豊田(章男社長)の熱い思いがなければ復活は不可能だったと思う。いちばんのハードルは社内だった。そんなクルマをつくって儲かるのか、売れるのか、ファン・トゥ・ドライブなんて時代じゃない…そういうものを乗り越えて、ここまでやっと来れた」

新型スープラの室内
電動化や自動運転などの分野では国際的な競争が激しさを増す一方、スポーツカーの開発環境は厳しい状況です。今回はドイツの自動車メーカーBMWとの提携によって復活にこぎつけました。生産はオーストリアにあるマグナ・シュタイヤー社への委託という形がとられます。このような様々な“工夫”が必要なあたり、昨今の自動車ビジネスの難しさをあらためて感じます。
思えばトヨタと日産…かつては日本の自動車産業のビッグ2と呼ばれました。国内シェア30%台でしのぎを削った時代もいまや昔。現在、トヨタは売上高30兆円超に対し、日産は11兆円あまり(それでも日本企業では五指に入る数字ですが)、国内シェアもトヨタが50%に届かんとするなか、日産は10%程度。お互いがそれぞれの道を歩んでいます。しかし、今回ほぼ同じ時期に行われた両社の発表には、アプローチこそ違えど、クルマの将来に向き合う姿が見えました。久々にワクワクする機会でもありました。
そして、両社が対照的なスタンスだった1970年代後半~80年代前半のころを思い出します。これについては次回お話しすることにいたします。(了)

イベントでは歴代スープラも勢ぞろいした