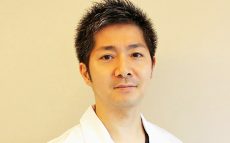それぞれの朝は、それぞれの物語を連れてやってきます。

びわ湖の花火大会(撮影:冴木一馬)
花火写真家で花火研究家の「ハナビスト」、冴木一馬さん。花火は一瞬の芸術ですが、ハナビストになるまでには長い道のりがありました。
大阪在住の冴木一馬さんは64歳。山形県鶴岡市の出身です。小さいころは人見知りで、変わった子だったと言います。
「勉強が大嫌いで、宿題もしない。廊下に立たされてもじっとせず、校舎のなかを探検するような小学生でした。高校生になるとヒッチハイクで札幌まで行き、ひと夏をパチンコ屋さんに住み込んで働いていましたよ」
父親がブティックを経営していたこともあり、高校を卒業するとファッションデザイナーを目指して、上野にある専門学校に入ります。その後、大阪のアパレル会社に就職。勉強のためにとファッションショーで写真を撮ったのがきっかけで、カメラに興味を持ち、休みの日は京都や奈良へ出掛けて写真を撮るようになります。
そして、たまたま写真雑誌に送った作品が佳作に。「俺には才能があるんじゃないか?」と勘違いしたのが、プロカメラマンへの第一歩でした。

冴木一馬さん(ペルーの花火取材に行く様子)
25歳で脱サラし、東京の出版社に「仕事をしたいのですが」と電話します。雑誌が飛ぶように売れる時代だったので、どの編集長も会ってくれました。しかし、作品を見た編集長に「では連絡しますから」と言われるけれど、電話が来ません。
それもそのはず、神社仏閣の写真を持って来た素人のようなカメラマンに、仕事が来るはずもありません。それでも冴木さんは諦めず、いろいろな編集部に連絡を取り続けたところ、何と『週刊文春』から仕事が来ます。
やる気が認められて、その後、専属カメラマンになります。364日は現場で、ゴミ箱に隠れて「特ダネ」を狙った日もありました。忘れられないのは、韓国の民主化運動を取材したときのこと……。
「デモ隊と軍が激突し、催涙弾が飛び交うなか、シャッターを切り続けたんです。どうにか撮影を終えて、ふと見たカメラバッグに穴が空いていました。ゾッとしましたね。銃弾が貫通していたんですよ」

報道カメラマン時代の冴木一馬さん
「毎日が戦争のようだった」と振り返る冴木さんに転機が訪れたのは、いまから34年前、30歳のときでした。
「地元大阪・天神祭の撮影を頼まれ、初めて花火を撮ったんです。花火は心が癒されるので、いいものだなと思いましたね。それから趣味で撮るようになったんですが、当時はネットもない時代で、市役所に電話して日程を調べました。そんなある日、小さな出版社から『花火の写真を貸して欲しい』と連絡が来て、花火特集を組んだ雑誌が売れに売れ、急に忙しくなったんです」
当時、花火の写真と情報を持っていたのは冴木さんくらいでした。写真を貸すだけで、ひと夏に思わぬ収入が入り、「これは儲かる。よし、これからは花火写真家一本でやって行こう!」と決意しますが、すぐに「勘違い」だと気づきます。
花火の仕事は、7月・8月の2ヵ月だけ。「それなら原稿も書こう。花火写真家と花火研究家なら、収入が2倍になるはず!」と考えます。
当時、エコノミストやコラムニストなど、横文字の職業が注目されていました。そこで花火の文化や歴史にも詳しい「ハナビスト」という肩書きを考え、花火師の資格を取り、講演会も開くようになります。

天橋立の花火大会(撮影:冴木一馬)
ところが、本業の写真はフィルムからデジタルの時代になり、デジカメが登場したことで、アマチュアでも簡単に花火が撮れるようになります。2000年以降は、写真を貸し出す仕事がほとんどなくなってしまいました。それでも冴木さんはフィルムにこだわり、デジタルのような加工はせず、常に客観的な報道写真として花火を撮り続けて来ました。
打ち上げ花火は1500度を超える高温で、さまざまな金属が燃え、あらゆる色の光を放つそうです。リチウムは赤、ナトリウムは黄色、カルシウムは橙、銅は青緑といったように。デジタルカメラでは、この微妙な色を正確に捉えることができません。
去年(2020年)、日本郵便の切手に冴木さんの写真が採用されました。もちろんフィルムで撮影したものです。切手シートには、ハナビスト・冴木一馬として、こんな文章が載っています。

オリジナルフレーム切手「日本の花火 2020」
「花火文化は国連加盟国193ヵ国のうち、約30ヵ国にしかありません。また私たち素人が楽しむ玩具花火は、半分の15ヵ国ほどにしかないのです。なぜなら西欧の多くの国々では、古くから人種や宗教の違いによる紛争が長く続き、例え玩具花火と言えども一般人に火薬を扱わせない文化が色濃く残っているからです。まさに花火は平和の象徴でもあるわけです」
ファインダーを覗くとき、どんな気持ちでシャッターを切るのか伺いました。
「花火は恋人のようなものかも知れませんね。綺麗なときはわずかな一瞬。だからその瞬間を残しておきたいんです」

(左)写真集『花火』/(右)写真集『花火景』
■写真集『花火』(出版社:光村推古書院)
■写真集『花火景』(出版社:赤々舎)
■ハナビスト・冴木一馬「それゆけ花火号」(GQ Japan)
https://www.gqjapan.jp/tag/fireworks-goes-around