ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム「報道部畑中デスクの独り言」(第404回)
昨年暮れに発表されたホンダ・日産自動車の経営統合検討開始から50日あまり。2月13日に協議の打ち切りが決まりました。経営統合が「幻」に終わったことで、今後の注目は次なるパートナー探しになります。

横浜の日産本社
特に日産は決算会見で公表された事業再生策の最後に「新たなパートナーシップの機会を積極的に模索」という文言が盛り込まれました。内田誠社長は「様々な分野におけるパートナーを探求していきたい」と自動車メーカー以外の連携も示唆した上で、台湾・鴻海グループとの接触については、「マネジメントレベル(経営陣)と話をしたケースはない」と述べました。
ホンダ、日産とも単独での生き残りが厳しいことは両社一致していますが、中でも日産の新たなパートナー探しは自動車ファンのみならず、気になるところです。
ルノーが持つ日産の株式は、直接保有の17.05%と信託会社分の18.66%の計35.71%で、資本関係を対等にするために、ルノーは信託会社分の段階的な売却を進めています。この信託会社の分がどこに渡るのかが大きな焦点です。
鴻海グループが取得に向けてすでに動きを見せており、台湾・鴻海精密工業の劉揚偉会長は「買収ではなく、協力」だと述べています。ただ、台湾企業ということで、外為法、経済安全保障の面で懸念する声もあります。だからこそホンダとの統合劇に、経済産業省が一枚かんだのではないかという説も出てくるわけです。

横浜の日産本社
一方、パートナーと日産の間に何かをかませると、いくらか事情は変わってきます。
投資ファンドがいったん取得することは、いの一番に考えられることでしょう。また、アメリカを経由する、例えば、鴻海に生産委託しているアップルの出資を受ける、半導体大手のエヌビディアとの提携、鴻海にアメリカ法人をつくるなど、そういう手法であればハードルが下がるのではないか……、そんな指摘も出ています。もちろん、これはトランプ政権の動向も大きく影響する可能性があります。
海外への技術流出の懸念から、国内勢との連携を望む声もあります。ホンダとの協議再開の可能性はゼロではないものの、厳しいのが現状です。そんな中、日産の系列会社OBは三菱グループが望ましいと語ります。日産は現在も三菱自動車と資本提携をしていますが、いわば「主客逆転」による関係強化というわけです。
三菱自動車は世界販売台数で日産の4分の1程度ですが、もともとは三菱重工業から1970年に独立した会社です。国産の量産乗用車の嚆矢は三菱の「A型」。さらに自動車事業に精通する三菱商事がバックにあります。前社長の益子修氏(故人)は三菱商事の自動車事業本部長出身でした。リコール隠しや燃費不正問題で業績を落とし、2016年に日産が筆頭株主となりますが、1990年代に日産が不振に陥った時には、「日産の背中が見えてきた」とも言われました。
ホンダと日産の経営統合協議打ち切りは、両社のスピード感における認識の違いが理由の一つと小欄でお伝えしましたが、旧財閥系の出自を持つ両社であれば、そうしたスピード感の違いもないように思います。思えば、ルノーもフランス政府が大株主で、スピード感という意味ではウマが合ったのかもしれません。

2月13日に開かれた日産の決算会見
また、EV=電気自動車に欠かせない電池開発の関係者も大胆な仮説を立てます。それは日産がトヨタの傘下に入ること。実現すれば「ウルトラC」ということになります。日産の財産の一つにEVがあります。世界販売台数でアメリカのテスラや中国BYDの後塵を拝していますが、日本勢ではトップランナー。技術もさることながら、何よりもこれまで販売されたEVの走行データがあります。
それは販売しないと得られないもの。100万台以上のデータは膨大であり、今後、EVを展開する上で、トヨタにとっては大きな魅力でしょう。独占禁止法というネックがありますし、何よりも日産の「プライド」が許すかという問題もありますが、実現すれば「オール・ジャパン体制」がいよいよ完成の域に達します。
これらの選択肢は確証があるわけではなく、日産にとっては余計なお世話かもしれませんが、なるほどと思わせる要素もないわけではありません。様々な視点で日産の行く末を案じている声だと思います。
「果たすべき役割に一日も早くめどをつけ、可及的速やかに後任にバトンタッチしたい」
2月13日の決算会見で経営責任について、日産の内田社長はこのように話しました。新たなパートナーが見つかった場合、現経営陣は刷新される可能性が高いですが、いずれにしても、トップには権力に拘泥しない人材を望みたいものです。日産はこれまで「救世主」によって、幾度の危機を脱してきました。が、その救世主は時を経るにつれ、「絶対君主」のような存在になっていきました。
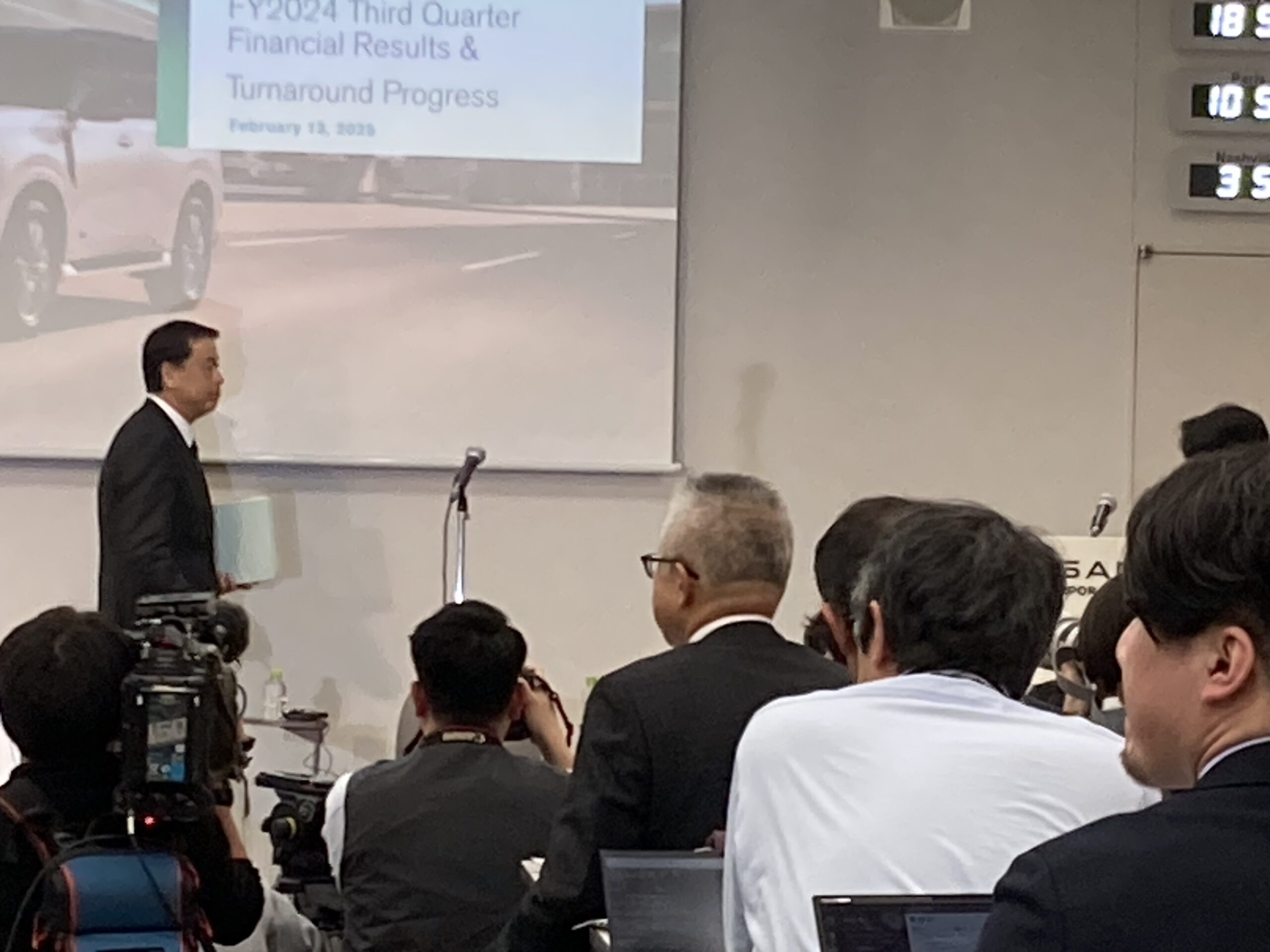
会見を終えた内田社長
カルロス・ゴーン氏は言うに及ばず、かつて「労働貴族」と呼ばれた元自動車総連会長の塩路一郎氏(故人)は、戦後間もない労働争議の際、経営寄りの第二組合をつくって労組を切り崩し、救世主的役割を果たします。しかし、その後は社内人事にも介入するなど権力を握り続けました。日産にはそのような絶対君主をつくってしまう伝統があるのでしょうか。そうした歴史を断ち切ることからすべてはスタートするのだと思います。
1999年の経営危機の時、当時のダイムラー・クライスラー(以下ダイムラー)、フォード、ルノーとの提携が取り沙汰され、結果、ルノーに落ち着いた経緯があります。ダイムラーとの交渉決裂後、当時の塙義一社長は急きょフランスに渡り、ルノーとの提携にこぎつけました。倒産の危機を間一髪乗り切ったと言われています。
当時とは事情は違うものの、何が起こってもおかしくない状況です。そして、新たなパートナー探しに残された時間は多くはないでしょう。
(了)





