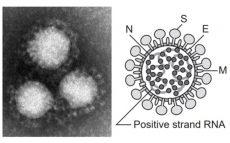ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」(12月2日放送)にジャーナリストの佐々木俊尚が出演。欧州加盟国向けの救済基金「欧州安定メカニズム(ESM)」について解説した。
欧州安定メカニズム(ESM)
ユーロ圏の財務大臣は11月30日、欧州債務危機の際に設けられた加盟国向けの救済基金である欧州安定メカニズム(ESM)を見直すことで合意した。
飯田)ヨーロッパの金融行政の安定を図るための金融支援機関で、財政危機に陥った国を支援するため、加盟国がお金を出し合う仕組みだということです。
佐々木)5年前にギリシャ危機というのがありました。ギリシャは放漫財政で、人口の4分の1ほどが公務員というような恐ろしい状況で財政破綻していました。そのとき、巨額の債務があってどうするかというので揉めました。
飯田)財政破綻させると、ユーロが紙きれになるのではないかと。

ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」
「ギリシャ危機」の際にEUとギリシャの間に残った禍根~欧州における南北の分断
佐々木)巨額の赤字をどうするかというので、当初債務を減免してデフォルトさせるという話でしたが、それをやると財政規律の問題があり、緊急資金注入し、お金を貸してあげました。ギリシャ政府がドイツやフランスの銀行にお金を大量に借りたのです。債務の減免で貸し借りなしにするのであれば、ギリシャの国民は助かったのですが、資金注入だと助かりません。なぜならEUからギリシャにお金を貸せば、貸したお金はドイツの銀行に返されるだけだからです。ドイツの銀行は助かりましたが、貸したお金はギリシャには残りませんでした。ギリシャには緊縮財政が求められて、窮乏を極めてみんな大変でした。「EUは何も助けてくれなかったではないか」という大きな禍根を残したのです。
飯田)切り売りした港が中国に買われるなど、安全保障上でも不安定になりましたね。
佐々木)今回もイタリアなどは、新型コロナが感染爆発しています。かなりコロナにお金をかけているので、今後財政がおかしくなります。GDPはマイナスになっていて、資金注入が必要になります。そこでドイツ、フランスという北の方の国が、生き延びるために南のヨーロッパを足蹴にするような構図になると、また同じ問題が再燃して、南北の分断が激しくなる気がします。
飯田)あのときユーロA、ユーロBにして、南の方の財政の悪い国たちはユーロBを使って、ドイツやフランスなど、いい国はユーロAを使うというような話も出ました。
EUにおける同胞意識~「国家とは何か」という根幹にかかわる問題
佐々木)そうなると、もはや統一通貨ではなくなってしまいます。1つの国のなかで金融財政政策を取れる……例えば日本は円という共通通貨があります。「東京は儲かっているけれども、北海道や四国は財政が厳しいから、東京で集めたお金を地方交付税としてそちらに回しましょう」ということになっても、それに対して東京の人は「そんなことはやめろ」とは言わないではないですか。
飯田)「何だよ」と思っていても、同じ日本ですから。
佐々木)これがヨーロッパではどうなるか。ドイツ人にすれば、「我々は長年緊縮財政をやって厳しい思いをしているのに、ダラダラと暮らしているイタリア人、ギリシャ人にお金をあげるのはけしからん」と怒ります。その気持ちもわかりますが、それを言い出したら、「EUというヨーロッパ全体は1つのネイションである」という発想に反することになります。そうすると「国とは何か」、「ネイション、国民国家の国民とは何なのか」という根幹に関わる問題になり、それがついに噴出しているのかなという感じがします。
飯田)経済の部分で先に統合はしたけれども、同胞意識は形や数字には表せませんが、いちばん重要なのはそこだったりしますよね。
佐々木)しかも、EUは冷戦後、東欧まで入り拡大しています。ドイツ人がトルコやチェコ、スロバキアに同胞意識を持てているのかどうかは微妙ですよね。グローバリゼーションやコスモポリタンということで、「世界は1つ」と言って来ましたが、そういう概念は本当に有効なのでしょうか。ASEANと日中韓が1つの国になって「東アジア共同体」のようなものができ、どこかの国で放漫財政が起きたときに、日本人は「同胞だから」とお金を投じられるかどうかということを、考えなければいけません。もちろん狭隘(きょうあい)な愛国心に走ってはいけませんが、バランスなのだと思います。
時代とともに変わる「同胞意識」
飯田)適切なサイズのようなものが各々あるのかも知れないですね。
佐々木)日本だって考えてみれば、日本人のアイデンティティができたのは明治維新以降です。
飯田)もともと江戸時代は各藩の体制だった。
佐々木)薩摩の人とか会津の人であって、日本人という意識はなかったと言われています。その時代だったら「北海道に支援などできない」と思っている人がたくさんいたかも知れません。時代とともに我々の「同胞」というエリアの広さ、意識は変わるのだと思います。
飯田)その辺がコロナであぶり出されたところがあるかも知れないですね。