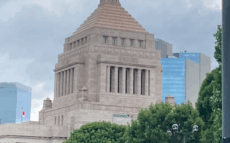新しい民主主義か? 馴れ合い民主主義か?
公開: 更新:
ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム「報道部畑中デスクの独り言」(第431回)
■政権という「魔物」
「せいけん」……、わが社の報道にある岩波書店発行の「広辞苑第六版」には「生検」から「請見」まで13の言葉が出てきます。その中で政権とは「政治を行う権力。政治権力。国の統治機関を動かす権力。『政府』とほぼ同義にも用いる」とあります。

いまは静かな永田町、秋になれば俄然動き出す
参議院選挙からまもなく1か月、衆議院に続いて、参議院でも少数与党となった政治状況の中、連立政権の枠組みが変わるのかどうか注目されています、自民党では両院議員総会で党総裁である石破茂首相が改めて続投を表明する一方、出席議員からは首相の早期退陣や総裁選の前倒しを求める声が相次ぎました。結局、党則に従い、総裁選を前倒しするかどうかを総裁選挙管理委員会に一任することになりました。
一方、野党はいずれも連立政権参画には否定的な考えです。先日、新しい執行部体制となった日本維新の会では、党内に連立容認論もくすぶる中、藤田文武共同代表が「石破政権とはあり得ない。安易な連立をすると党の存在価値がなくなる」と述べています。
政界はつかの間の「凪」の状態ですが、9月に入ると政界は大きく動き出す可能性があります。
■「政界秋の陣」まもなく。自民党、そして野党の本質とは?
ここで自民党の本質について考えてみます。国民政党、保守政党、現行憲法の自主的改正を党是とする……、「自称」も含めて自民党を形容する際に使われるフレーズですが、私はそのどれもが本質には当てはまらないと思います。では何か。いみじくも党のホームページ冒頭にこのように書かれていました。
「この国を動かす責任がある」
言い換えれば「政権に対する執念」です。政権を握り続けることが党の求心力の源泉であり、そのためには何でもするということです。誤解を恐れずに言えば、政権維持がどんな政策や理念にも優先されるのです。
1955年の保守合同以降、自民党は国政選挙で何度も過半数割れに見舞われました。しかし、その都度、統一会派や連立を組むことで政権を維持してきました。古くは新自由クラブ、社会党、新党さきがけ、自由党、保守党など。特に思想信条に大きな違いがある社会党と手を組んだことは当時、大きな衝撃を与えました。
しかし、これら政権に参画した政党はいざ一翼を担うと、次第に埋没して存在感を失い、解党や所属議員が自民党に合流する歴史を繰り返してきました。一方、自民党は政権を明け渡した時期もありましたが、ほどなく奪還します。現在も公明党との連立政権を続けています。政権に対する強い執念の賜物と言えましょう。
「いまはバラバラだけど、政権を取ったらまとまる。それまでの我慢だ」
以前聞いた旧民主党有力議員の秘書の一言です。この議員はすでに政界を引退していますが、かつて自民党に所属していました。秘書のつぶやきはそれを念頭にしたものと思われますが、実際には民主党は政権を奪取してもまとまることなく、約3年で瓦解しました。
こうして見ると、自民党と野党の違いは「政権に対する執念」、その一点と言えます。「政権奪還」と啖呵を切る政党もありますが、なり切れない背景にはもちろん「数」の問題もありますが、政権への執念より優先する何かがあるのだと思えてなりません。それとも、野党にとって政権は「魔物」なのか……。
■居心地良い状態、あいまいな責任の所在、行きつく先は?
「いまの状況は、与野党双方にとって居心地のいい状態なのではないか?」
最近、取材先でこんな声をよく聞きます。与党は衆参両院で過半数割れという、これまで経験したことのない状況にはあるものの、非自民の連立政権ができない限りは、自民党中心の政権であることに変わりはありません。所属議員にとっては、政権を握っている限りは党にいた方が安泰、政権を手放してまで党を割る必要はないということになります。
一方、野党は交渉次第で自らの掲げる政策を実現できる素地ができました。しかし、野党でいる限り、政権という重い「責任」が生じることはないわけです。ハング・パーラメント(宙づり国会)、パーシャル(部分)連合という言葉が躍りますが、奇妙な安定がそこにはあります。
以前の小欄でもお伝えした各党トップの発言を改めて振り返ります。
「新しい時代に入った。熟議と公開の時代に入ってきた」(立憲民主党・野田佳彦代表)
「ある意味でこういう状況は、民主主義にとって望ましいことかもしれない。より議論が精緻になるということ」(石破首相)
「与党は“寛容と忍耐”、野党は“責任と提案”。国益にかなう国会を作り上げていこうという意識が両者に新たに課せられた義務」(国民民主党・玉木雄一郎代表)
政権は大きな権力ではありますが、同時に応分の責任も伴います。三権分立の中で国会はもちろん、行政府として官僚を束ね、時には司法とも対峙する立場を担います。一方で、権力の分散は決して悪いこととは言えないものの、時に責任の所在をあいまいにします。
「スピードのある決定が鈍ることは想定しておかなくてはいけない」
参院選の結果を受けた経団連の筒井義信会長の発言です。まさに「決められない政治」につながる懸念です。また、様々な政策に手を広げることで財政の悪化を危惧する声も経済界から聞かれます。様々な組織に当てはまることですが、こうした組織は運用を誤れば内外の信頼を失います。まして国であれば、大きく国益を損なうことになりかねません。
1人1人の議員は必死に活動しています。しかし、それが塊になるとどうなるか……。「新しい民主主義」として歴史をつくっていくのか、「馴れ合い民主主義」に陥るのか…いまの政治状況はその分水嶺の上にあると言ってもいいでしょう。投票によってそのような政治状況をつくり出した私たち有権者も、その動きを注視する責任を負っています。
(了)