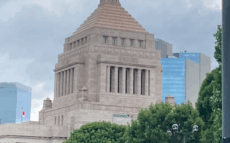自公連立解消で混沌とする首班指名の行方
公開: 更新:
ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム「報道部畑中デスクの独り言」(第442回)
■12年の歳月を経て適中した故・石原慎太郎氏の“予言”
安倍首相との党首討論に臨んだ。 14 分近くにわたる“スピーチ”。憲法については「屈辱的な戦後史の象徴。いろんな盲点があります。これは本当に随所を大幅に改革する必要がある」と早期の改正を訴えた。それにからみ、「必ず、公明党はあなた方の足手まといになりますな」とも。周囲から「失礼だ!」とヤジが飛んでも「いや、本当のことを言っているんだ。君ら反省しろよ!」と一歩も引かない。

国会は見たことのない景色が繰り広げられるのか?
拙著「憎まれて死ぬか、愛されて死ぬか。政治家石原慎太郎の日々」(ブックマン社)で記した2013年4月17日の党首討論。安倍晋三首相に対して日本維新の会の石原慎太郎共同代表が放った一節です。「公明党が足手まとい」かどうかはともかく、石原氏の“予言”が12年の月日を経て現実のものとなりました。
「政治とカネに関する基本姿勢で相違があった。自公連立政権はいったん白紙とし、これまでの関係にけじめをつける」
2025年10月10日夕方、自公党首会談後、公明党の斉藤鉄夫代表は記者会見で、言葉をかみしめるように語りました。四半世紀以上続いた「自公蜜月」にピリオドが打たれた瞬間でした。これに対し、斎藤代表の会見後に報道陣の前に姿を見せた自民党の高市早苗総裁は「一方的に離脱を伝えられた。大変残念だ」と不快感を示しました。両者の認識のずれが改めて浮き彫りになった1日でもありました。
■見逃したサイン、軽んじた公明党幹部の発言
公明党が連立を離脱した理由は表向き「政治とカネの問題の対応」ですが、その後、「高市総裁になった時点で離脱ありきだった」「ある国への忖度ではないか」など、「状況証拠的」な分析が飛び交っています。その真偽は定かではありませんが、自民党が公明党の発していた「サイン」を甘く見ていたことは間違いないようです。
思えば、かつて公明党幹部が発する発言には、すべてに意味のあるメッセージを含んでいました。私が国会担当を始めた1998年、時は小渕恵三政権。公明党は当時野党でした。いまでも衆議院内には第5控室に「野党クラブ」という野党担当の記者クラブがありますが、当時は隣接する部屋に記者会見のスペースがあり、神崎武法代表の会見はそこで行われていました。やり取りは「禅問答」のようで、ある話題について、それまではずっと「NO」と言っていた発言が消えることで、「実はYES」という言外に潜むメッセージを発していました。そして、番記者もそれを敏感に感じ取っていました。ちなみに私は鈍感で、そのメッセージを見落とし、慌てた苦い経験があります。
また、小泉純一郎政権の時、8月15日に小泉首相が靖国神社を参拝するかが大きく注目されていたころ、公明党の冬柴鉄三幹事長はニッポン放送の番組に出演し、「(8月15日に)総理は参拝されないと思いますよ」と明言。これが政治面トップとなる大きなニュースになりました。そして、小泉首相は参拝を“前倒し”して13日に行い、お盆休みにメディアは不意打ちをくらいました。
連立解消の“通告”を受けた時、高市総裁は「自民党総裁が私でなければ連立離脱はないのか、総裁が代われば連立協議はあるのか」ときいたといいます。公明党からしてみれば、無粋と感じたでしょうが、公明の回答は「誰が選ばれても同じだ」。これは高市総裁だからダメではなく、その後の振る舞いや党役員の陣容に納得がいかなかったという意味に私はとれます。つまり、高市体制でも執行部のメンバーによってはここまでのことになっていないということではないでしょうか。そのメンバーについては様々な名前が出ていますが、公明党が腹を割って話せる人材がいなくなったということに尽きると思います。

自民党本部
10月4日に高市新総裁誕生直後に開かれた自公党首会談で、斎藤代表は「政治とカネの問題のけじめ、企業・団体軽金の規制強化」「歴史認識と靖国神社参拝」「外国人との共生」の三点に関し、「多くの支持者が心配している。それらの解消なくして連立政権はない」と伝えました。自民党は公明党が「連立解消の可能性」を切り出すこと自体がただならぬ「サイン」と感じ取るべきだったのだと思います。それは私どもメディアも同じで、野党時代も含め、両党の「二人三脚」の時代が26年続いたことで感覚がマヒし、公明党幹部の発言の重さを軽んじていたということになるのでしょう。ただ、その後、公明党幹部は首班指名をめぐる発言がぶれているとも伝わってきます。発言が軽くなればなるほど、公明党の存在意義は薄れていくことも肝に銘じるべきでしょう。
ちなみに今回の連立解消劇を「熟年離婚」に例える人もいるようです。離婚というのは往々にして、長年の不満が積もり積もって、ある一瞬がトリガーになるということが多いもの。26年を振り返ると、なるほどそんな一面もあるのかもしれません。……と、そんな話を家族にすると、「私たちも気をつけなきゃね」と言われ、場が凍り付きました。閑話休題。
■進む「分断」、有権者の判断基準はより明確に?
ただ、この状況は、有権者にとっては非常にわかりやすいものになったと言えます。少なくとも投票行動の上で、自民党支持=公明党支持の図式に縛られることはなくなりました。もちろん、1~2万票ともいわれる「公明票」の恩恵を受けられなくなった自民党議員は少なくありませんし、与党という立ち位置を失った公明党議員もまた苦しい戦いを強いられるでしょう。しかし、「他力本願」でなく、自身の“足腰”を鍛えるにはいい機会かもしれません。特に自民党にとっては文字通りの「解党的出直し」となるでしょう。もし、党内でこの筋書きを描いている人がいるとすれば、かなりの「策士」と言えるかもしれませんが、さて…?
10月21日と目される首班指名選挙は公明党が連立を解消したことで多数派工作が激しくなっており、与野党、野党内で幹部による会談が重ねられています。「引く手あまた」の国民民主党と日本維新の会。国民民主党の玉木雄一郎代表は共同歩調をとるには安全保障やエネルギーなど、基本政策の一致が大前提という姿勢を記者会見などで示しています。一方で、日本維新の会は自民党と連立政権樹立に向けた政策協議を始めました。首班指名選挙までに合意に達するかが焦点です。
多くの国民は政権の枠組みがどうであれ、物価高の中、少しでも生活が楽になることを望んでいるはずです。自ら掲げる政策を実現するには、何が近道なのか……。各党がそれぞれ掲げる理念をどう貫いていくのか、世間の目が注がれています。
ネットにあふれる意見を見て感じるのは、日本でも「分断」が進んでいるということです。とにかく両極端の書き込みが飛び交っています。「米国がくしゃみをすると、日本も風邪をひく」とは主に経済に関して言われる言葉ですが、実は政治の面でもそうなりつつあるのかもしれません。分断は欧州にも押し寄せており、「民主主義の危機」とも言われます。その渦に日本も巻き込まれていくのか、乗り切る知恵が問われています。事態は刻々と動いています。(文中の肩書はいずれも当時)
(了)