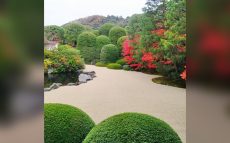昔は「天気」をどうやって予測していたの?
公開: 更新:
あなたの朝がいつもイイ朝でありますように---ニッポン放送『羽田美智子のいってらっしゃい』。5月29日放送分のテーマは「天気予報」です。

※画像はイメージです
天気は私たちの生活と深く関係しているため、古くから「天気の予測」がとても重要でした。紀元前4世紀ごろ、古代ギリシャの哲学者・アリストテレスは天気のパターンを観測し、気象に関する本を書いたとされています。
当時は科学が発達していなかったため、空や雲を観察し、その様子などから経験的に天気を予測していたそうです。例えば「夕焼けの次の日は晴れ」「太陽に光の環がかかると、次の日は雨」という感じです。
17世紀になると温度計や気圧計が発明され、気温や気圧など気象に関するデータを参考に、天気の研究が進んでいきました。
1820年には、ドイツの気象学者であるハインリヒ・ブランデスが、地図に「気圧の分布」を表したものを発表します。現在の「天気図」にあたるもので、これを使って予測したのが「初めての天気予報」と考えられているそうです。
その後、ヨーロッパやアメリカで天気予報が始まります。日本でも明治時代、「国の発展のために必要」だとしてヨーロッパから技術者を招き、天気予報に向けた観測が始まりました。
そして1884年(明治17年)、日本初の天気予報が発表されます。それ以降、天気予報は私たちの生活に欠かせないものとなっています。