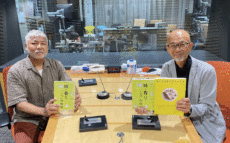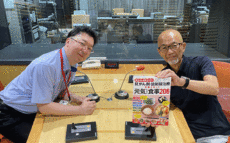千葉県市川市南行徳にある加藤海苔店の店主・加藤洋一さんが、上柳昌彦アナウンサーがパーソナリティを務める、ラジオ番組「上柳昌彦 あさぼらけ」内コーナー『食は生きる力 今朝も元気にいただきます』(ニッポン放送 毎週月・金曜 朝5時25分頃)にゲスト出演。約40年にわたり海苔の買い付けや販売に従事している加藤さんに、行徳産の海苔の特徴、海苔を作る職人が激減している現状、千葉の海苔作りの歴史、秋の風物詩である海苔の種付け作業について聞いた。
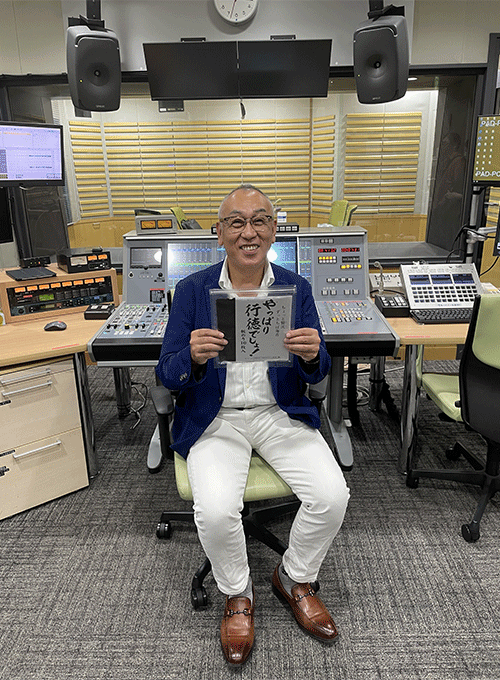
香りと甘みに優れている行徳の海苔
上柳:加藤海苔店は、東京メトロ東西線の南行徳駅のすぐ近くにありますが、「千葉の海苔?」「東京湾で海苔?」と思う方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。行徳産の海苔にはどんな特徴があるのでしょうか?
加藤さん:一般的に千葉の海苔は、香りがよくて甘みがあるんですが、中でも行徳産の海苔は、香りと甘みに優れています。
上柳:行徳の近くには大きな江戸川が流れていますが、実はこの川が海苔作りを支えているのだそうですね。
加藤さん:海苔は必ず、真水と海水の混ざり合ったところで取れます。ですから、海苔作りで最も大切なのは「川が流れていること」です。
上柳:栄養分は川が運んできてくれる、とよく言いますよね。海苔にはどういう栄養素が必要なんですか?
加藤さん:海苔の成長には、リンと窒素が欠かせません。幸い、この行徳には江戸川という大きな川が流れており、その栄養分が海苔作りにとても適しているのではないかと私は思います。
上柳:行徳でとれた板のり「やっぱり行徳でしょ!」という商品を頂いたのですが、味がすごく濃くておいしいんですよ。
加藤さん:そこが特徴です。
上柳:香りも強く味のインパクトも強いので、お醤油とかをつけなくても、このままバリバリといつまでも食べたくなります。こんなに味が違うものなんですね。
加藤さん:やっぱり江戸川の栄養分が、すごく海苔の成長に適しているから、おいしいものがとれるじゃないかと思っています。
かつて100人いた海苔師が今はわずか4人に
上柳:このおいしい海苔を、何人ぐらいの方で作っているんですか?
加藤さん:今は4人です。
上柳:4人!
加藤さん:かつては100人以上いたんですけどね……。今は4人の方がおいしい海苔を作ってくれています。
上柳:4人とはちょっと衝撃的です。海苔づくりの工程などを聞いていますと、かなりの手作業と重労働がありますよね。
加藤さん:4人で作っていますから、どうしてもたくさん作れないわけです。行徳の海苔は本当においしいんですけど、なかなか市場に出回りません。
上柳:漁業は今高齢化が進んでいますが、行徳の海苔師の皆さんはおいくつぐらいなんですか?
加藤さん:いま海苔をとってくださっている漁師さんは、2代目で40代から50代の方が多いので、結構若いんですよ。なので、まだまだ安泰かもしれません。せっかくおいしい海苔作りをしてくださる方がいて、おいしい漁場があるので、我々も一生懸命やっていかなくちゃいけないなと思いますよね。
上柳:加藤さんは、行徳で生まれて育って、加藤海苔店の3代目ということですが、お店は創業してどのくらいなんですか?
加藤さん:昭和8年の1933年に創業したので、今年で92年目です。
上柳:昔から後を継いで海苔屋さんをやろうと思っていたんですか?
加藤さん:いえ、思っていません(笑)。でも、長男として生まれた宿命、使命ということで、小さい頃から後を継ぐことは頭の片隅にちょっとありました。
上柳:お店を任されることになって、すぐにこの世界に入れるものなんですか?
加藤さん:経験が必要な仕事だから、若手が入ってもすぐには何もできません。
ただ、海苔の買い付け入札があるんですけど、父は私が若い頃からよく連れて行ってくれました。その経験で、「この海苔はおいしい」「この海苔は大したことない」といった感覚を自然と教わることができました。それはとても嬉しかったし、今でも役立っています。
上柳:加藤海苔店を継ぐことになったのが40年前、1980年代半ばだと思います。世の中はこれからバブルに向かおうとしていて、日本全体がどこかウキウキした雰囲気に包まれていましたが、その時の海苔はどういう存在だったんですか?
加藤さん:今でもそうですが、海苔ってなかなか主役になれない食べ物なんです。でも私としては、名脇役だと思っているんですよ。映画で言うと助演男優賞。そういう存在なのかなと思っています。
千葉の海苔作りの歴史
上柳:千葉の海苔作りの歴史は古いのですか?
加藤さん:千葉の海苔作りは、1821年に江戸の海苔商人・近江屋甚兵衛によって始められたと言われています。当時は千葉市や市原市、浦安、行徳、船橋、幕張、木更津など、東京湾の広い範囲で海苔の養殖が行われていました。
行徳という場所はもともと、塩作り、塩田が盛んだったんです。徳川時代の話に遡りますが、行徳では塩作りを奨励されていたので、塩作りが盛んな町だったようです。
上柳:幕府から塩を作るよう、命じられていたのですね。
加藤さん:その後、明治時代になると塩だけでなく、浦安などの漁区を借りて海苔づくりを始めた方もいたようですが、正式に海苔作りを始めたのは戦後です。なので、他の産地から比べると歴史が浅くなっています。
秋の風物詩、海苔の種付け作業とは
上柳:ちょうど秋というのは「海苔の種付け」のシーズンだそうですが、どういう作業なんですか?
加藤さん:海苔の種付けとは、簡単に言えば「海に張る海苔網に、海苔の胞子を付ける作業」です。
春から夏にかけて牡蠣の殻に胞子を植え付けると、胞子はどんどん増えて殻の裏の白い部分が真っ黒になります。その牡蠣を水中に吊るし、海苔網を取り付けた大きな水車を回すと、水中に漂う胞子が海苔網に付着します。
ただし、胞子が網に付いたかどうかは肉眼では確認できません。そのため電子顕微鏡で確認し、胞子が付いている網は冷蔵庫で保存します。
そして、海水温が海苔の成長に適した温度になると、初めて海に海苔網を張り出し、あとは自然の力で海苔がどんどん大きくなっていくわけです。
上柳:海苔が食卓に届くまで、大変なご苦労がいろいろあるのですね。
――海苔は、その香りとうま味、豊富な栄養で、日本の食文化を支える大切な食材だ。おにぎりや巻き寿司など、シンプルに食べるだけでも十分おいしく、味を一段と引き立ててくれる。
かつて100人以上いた行徳の海苔師も、今はわずか4人で作っている。川と海の恵みと、職人の丁寧な仕事が積み重なって生まれた海苔だと思えば、より一層おいしく感じられるかもしれない。
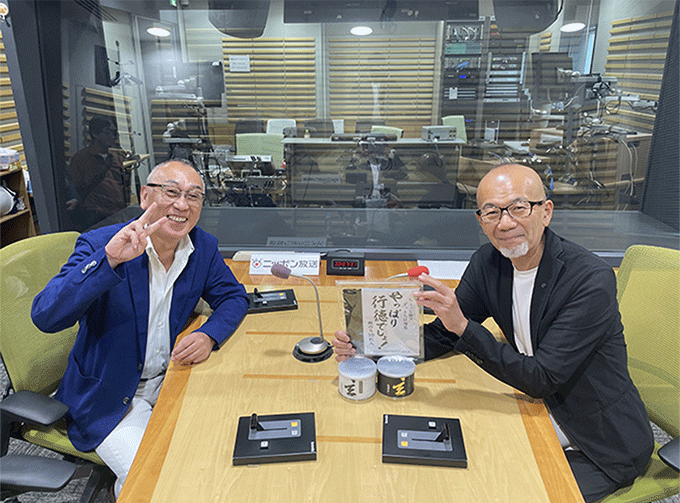
加藤海苔店の店主・加藤洋一さんと、上柳昌彦アナウンサーの詳しいトーク内容は、「食は生きる力今朝も元気にいただきます」特設コーナーHP(https://www.1242.com/genki/index.html)から、いつでも聞くことが可能だ。
番組情報
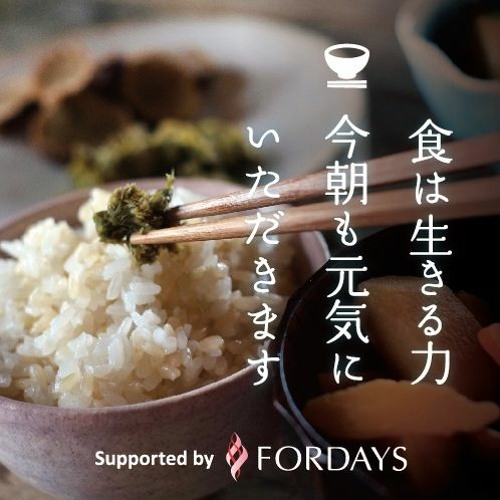
「上柳昌彦 あさぼらけ」内で放送中。“食”の重要性を再認識し、「食でつくる健康」を追求し、食が持つ意味を考え、人生を楽しむためのより良い「食べもの」や「食事」の在り方を毎月それらに関わるエキスパートの方をお招きしお話をお伺い致します。
食の研究会HP:https://food.fordays.jp/