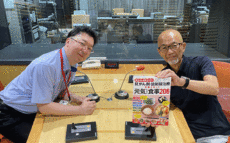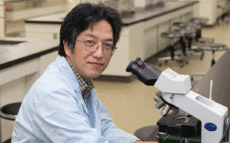砂糖で代用できる? 料理でみりんを使う科学的な理由とは
公開: 更新:
農学博士で調理科学者、味の素株式会社の研究者である川崎寛也さんが、上柳昌彦アナウンサーがパーソナリティを務める、ラジオ番組「上柳昌彦 あさぼらけ」内コーナー『食は生きる力 今朝も元気にいただきます』(ニッポン放送 毎週月・金曜 朝5時25分頃)にゲスト出演。料理にまつわる科学的な根拠やデータを知る川崎さんに、みりんや塩の調理効果、煮崩れを防ぐ方法、魚をしっとりした食感に仕上げる方法などを聞いた。
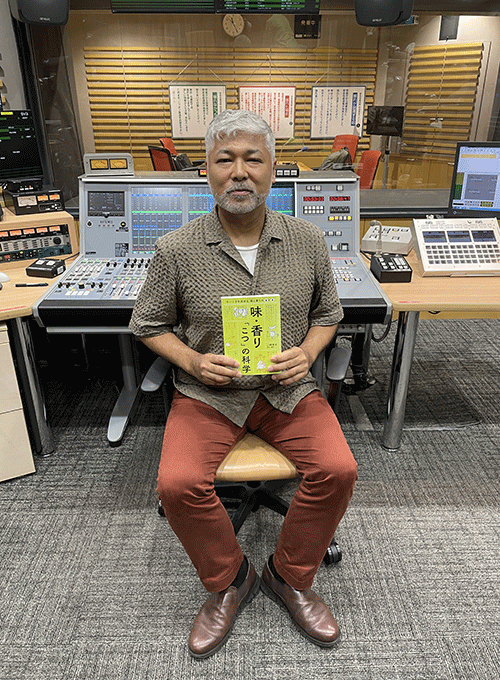
料理を科学的に考える
上柳:「調理科学」とはどのような学問なのですか?
川崎さん:料理を科学的に考える学問なんです。日本には日本調理科学会という学会があり、50年以上の歴史を持つ、世界でいちばん早く研究を始めた学会です。
上柳:世界に先駆けて、料理を科学的に捉えて分析していたのですね。
川崎さんのご実家はかつて西洋料亭を営まれていて、幼い頃から料理に囲まれた環境だったとは思います。大学は京都大学大学院農学研究科博士後期課程を修了、その後、味の素株式会社食品研究所に勤務されていますが、食に関心を持ったきっかけはどのようなことだったのでしょうか。
川崎さん:小学生のときに料理漫画が流行って、すごくハマって。
上柳:『美味しんぼ』ですか?
川崎さん:はい。『美味しんぼ』って、料理と化学みたいなことも書いてあるんですよ。さらに、料理番組を見てシェフにも憧れましたが、料理のすべてを理解したいと思い、科学者として一歩引いた視点で料理を学ぶ道を選びました。
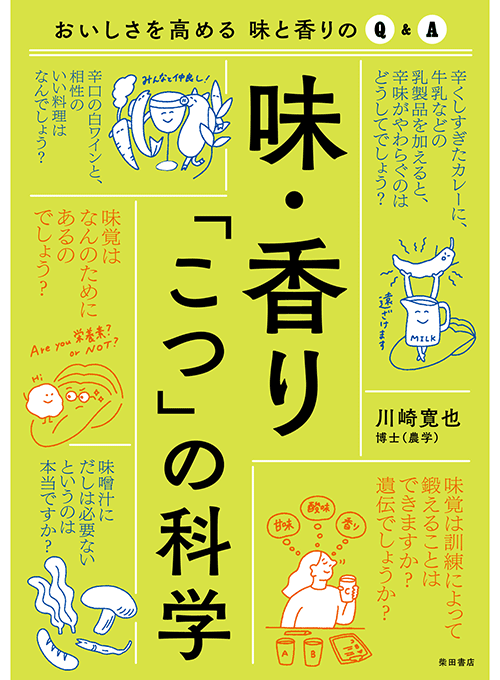
砂糖では代用できない、みりんの調理効果とは
上柳:みりんって、砂糖では基本的に代用できないのだそうですね。
川崎さん:甘い味をつけたい時は、砂糖を使っても問題ありません。ですが、みりんには野菜を少し固くしたり、煮崩れ防止、魚を柔らかくする、パサつき防止などといった調理効果があるので、砂糖とは違うわけです。
上柳:砂糖を使えば味は変化するけど、煮崩れ防止などの効果は出ないのですね。
川崎さん:みりんは、もち米を米こうじで発酵させ、焼酎を加えて作られます。焼酎を加えるから発酵が止まり、そのあと熟成させるので、お酒と違って甘みが強いわけです。みりんにはアルコールも入っていますから、昔は飲んでいたそうですよ。
上柳:みりんを飲む?!
川崎さん:そうなんです、江戸時代ぐらいでは、みりんに焼酎を入れて飲まれていました。当時は砂糖が貴重品ですから、みりんの方がよく使われていました。
上柳:みりんを料理に取り入れることで、照りや艶が出たり、肉崩れ防止、におい消し、パサつきを抑えたりなど、なぜそういう効果が出るのでしょうか?
川崎さん:料理は「水との戦い」みたいなところがあるのですが、糖というのは分子構造上、水をすごく吸着しやすく、水と馴染みがいいんです。
野菜や肉の多くは、水分が90%前後を占めています。たとえば茄子は95%以上が水分で、ほとんど水といってもいいほどです。調理の過程でこの水分が抜けてしまうと、どうしてもパサついてしまいます。だからこそ、水分をどう保持するかが大切なんです。肉料理でよく言われる「肉汁を逃がさないこと」も同じ考え方ですね。
上柳:みりんは、食材の水分を保持してくれるのですね。
川崎さん:みりんを使うと料理にツヤが増しますよね。あれも水の働きです。なぜツルッとした表面になるかというと、糖が水分をしっかり抱え込んで、表面に水分を残してくれるからなんです。
上柳:みりんを加えると煮崩れしにくいというのは、どういう仕組みになっているのでしょう?
川崎さん:煮崩れを防ぐためにみりんを使うのは、みりんに含まれるアルコールの効果です。ですから、煮切りみりんではアルコールが飛んでしまうので、この効果は得られません。
野菜でいうと、かぼちゃや小芋の煮物が代表的ですよね。野菜には細胞の周りに「細胞壁」があり、その成分はペクチンです。このペクチンは90℃以上になると水に溶けやすくなり、細胞が剥がれてしまいます。これが「煮崩れ」の正体です。
アルコールには、このペクチンが水に溶けやすくなるのを防ぐ働きがあるため、みりんを加えると煮崩れを防げるのです。
上柳:みりんが野菜の表面を支えてくれているわけですね。
しっとり食感を塩だけで引き出す
川崎さん:味付けで最も重要なのは「塩加減」だと思っています。なぜなら、人間の体は約0.9%の塩分濃度でできているからです。ですから、それより濃いと「しょっぱい」と感じ、薄いと「それほど塩味を感じない」という仕組みになっています。
上柳:0.9%の塩分が基準なんですね。
川崎さん:なんで「これが一番おいしい」と感じるのか。それは、甲状腺の維持という働きが関係しています。食べ物というのは体にとって異物ですよね。その異物が体の中に入ってくるわけですが、体はできるだけ何も変えたくないんです。
上柳:ずっと同じ状態でいたいわけですね。
川崎さん:味だけではなく、塩にはいろんな調理効果があります。
一番よく知られている塩の使い方が「塩を回す」ことです。特に日本料理でよく用いられます。例えば魚に塩をふってしばらく置き、その後に焼く。これは単なる味付けのためだけではありません。
塩の打ち方には2種類あって、ひとつは、しょっぱさを得るための塩。鮎の塩焼きのように、塩をふってすぐに焼く方法です。もうひとつは、しっとり感を出すための塩。塩をふって30分から1時間ほど置いてから焼くことで、仕上がりが変わります。
上柳:塩をして時間を置くと、なぜしっとり感が出るのですか?
川崎さん:そもそもなぜパサつくかというと、筋肉を作っているタンパク質が原因です。タンパク質は水分を抱えていますが、加熱するとその水分が一気に外に出てしまい、パサついた仕上がりになるんです。これを防ぐために塩をふると、一部のタンパク質が塩に溶け、ゲル化します。
上柳:塩をふると、魚の表面にゲル状の膜ができて、水分の流出を防いでくれるんですね。
なぜ、パスタを茹でるときに塩を入れるのか?
上柳:パスタを茹でるとき、なぜ塩を入れるのでしょうか? 人によっては、「塩を入れる必要はない」と言う方もいますよね。
川崎さん:これは科学的に「最高の味を作る」というより、料理人や作る側の好みによる部分が大きいです。
例えば、うどんは生地を練る段階で塩を加えるので、麺の中に塩味が含まれていますが、パスタは生地には塩を加えません。ですから、茹でるときに少し塩を入れることで、味がなじみやすくなります。まったく塩味のない麺より、少し塩味のある麺とソースを合わせた方が、おいしく仕上がるわけです。
上柳:たしかに、少し塩味のある麺の方が、ソースとの相性が良さそうです。
川崎さん:もうひとつ重要なのが食感です。イタリアでは、パスタをある程度カチッとした食感に茹でるのが好まれ、特に南イタリアでは表面がしっかりした麺が人気です。これは水が硬水で、ミネラルが多いことも関係しています。硬水に塩を加えると、ちょうどそのカチッとした食感になるんです。
一方、日本の軟水で同じような食感を出すとなると、塩分濃度を2~3%にする必要があります。しかし、この濃度で茹でると麺がしょっぱくなってしまいます。山形の有名シェフは、2%の塩で茹でた後に麺を洗うことで調整しています。ただ、家庭で作る場合はちょっと手間なので、塩分1%くらいが扱いやすいし、おいしく仕上がりますよ。
――料理の「こつ」は、料理上手な人だけが知っている勘や経験値ではなく、実は科学的な理由がある。「なぜ、この調味料を使うのだろう?」「なぜこのタイミングで入れるのか?」といった素朴な疑問も、科学的な根拠を知れば納得できる。理解が深まれば自信につながり、いつもの料理がもっとおいしく仕上がるかもしれない。
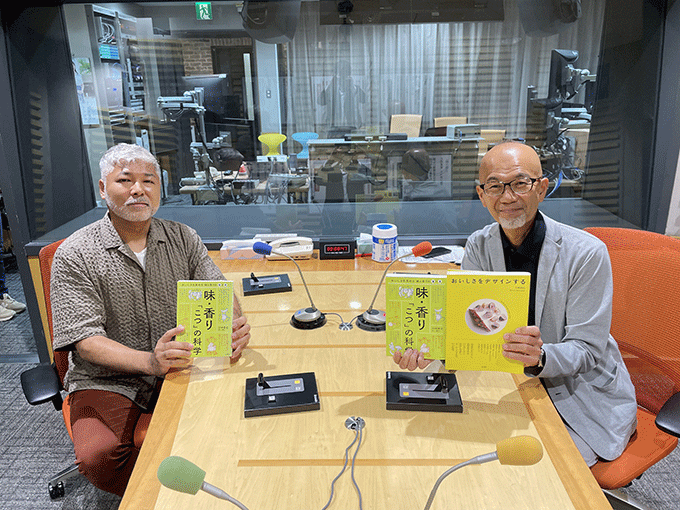
調理科学者の川崎寛也さんと、上柳昌彦アナウンサーの詳しいトーク内容は、「食は生きる力今朝も元気にいただきます」特設コーナーHP(https://www.1242.com/genki/index.html)から、いつでも聞くことが可能だ。
番組情報
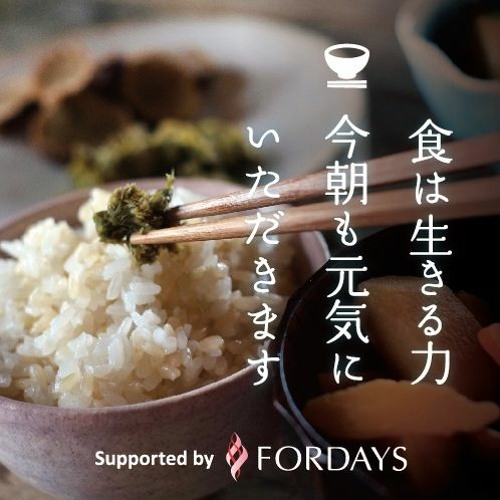
「上柳昌彦 あさぼらけ」内で放送中。“食”の重要性を再認識し、「食でつくる健康」を追求し、食が持つ意味を考え、人生を楽しむためのより良い「食べもの」や「食事」の在り方を毎月それらに関わるエキスパートの方をお招きしお話をお伺い致します。
食の研究会HP:https://food.fordays.jp/