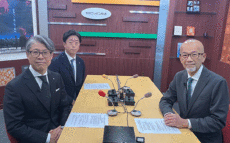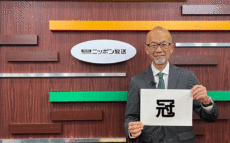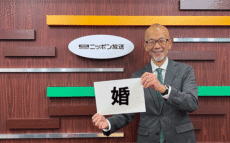お焼香、何回するのが正解?
公開: 更新:
日本に古くから伝わる「人の一生」にまつわる風習「冠婚葬祭」は、誰もが一度は通る、無くてはならない「人生の道標」のようなものです。「明日はもっといい日になる」(「上柳昌彦 あさぼらけ」内、毎週水曜日・午前4時40分ごろ放送)では、全国の聴取者の方からのおたよりをご紹介しながら冠婚葬祭の大切さをお伝えしています。

実際の葬儀会場のひとコマ
(神奈川県川崎市・伊勢では着物パートナーはガロさん)
葬儀の時のお焼香って、どの指であの藁みたいなモノを(?)つまむんでしょうか?私はいままで、親指と人差し指、中指の3本でつまんでいました。あと、焼香の回数も、2回なのか、3回なのか、周りを見ながら確認してやっていました。でも、知人が言うには親指と中指と薬指の3本でつまみ、焼香は3回というんです。先日亡くなった知人の葬儀に参列した折、京都にある仏教系の大学を卒業した人から聞きました。今後は迷わずに済みそうです。
お焼香のやり方や回数は、宗派によって異なります。ただ、たいていの場合、お焼香は、「親指・人差し指・中指、3回」の所が多くなっているようです。気になる方は葬儀に際して宗派を確認しておくのがいいかもしれません。(葬儀所によっては参列者が多い場合など、司会の方が、1回焼香を案内する場合もありますね)
日本の葬儀が大きく変わった「明治時代」
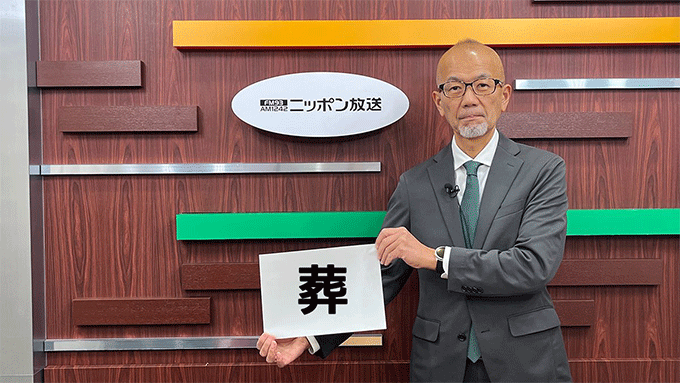
さて、「喪中はがき」が届く時期になりました。ハガキをきっかけに、今年亡くなった方に改めて思いを馳せることも多いですね。日本の葬儀の形が大きく変わったのは、じつは「明治時代」のことです。一番大きな変化は、「土葬」から「火葬」への変化。江戸時代は「土葬」の地域も多くありましたが、明治30年代以降、都市部を中心に人口が増え、お墓の場所が足りなくなったこと。加えて、伝染病予防法が制定されたことで、「火葬」が中心となりました。
「喪服が白から黒」へ変わったのも、明治時代のことです。元々、日本の葬儀では、亡くなった方に心を寄せようと、白装束に合わせて白い喪服を着るのが一般的でした。しかし、明治に西洋の文化が入って、日本の喪服も「黒」へと変化し始めます。その後、戦争の時代になって、葬儀が相次いだことで、汚れが目立ちにくい黒が重宝されて、いまでは黒が一般的になっているんですね。
ちなみに、日本初の「葬儀社」が生まれたのも、明治時代のこと。11月19日には、厚生労働省より認定を受けた「葬祭ディレクター技能審査」の実技試験が、全国8つの会場で行われました。大切な方を送る際は、やはり、プロのノウハウを持った方にお世話になるのが心強いですね。
「あなたのまちの冠婚葬祭・ある?ある!話」を教えて下さい!
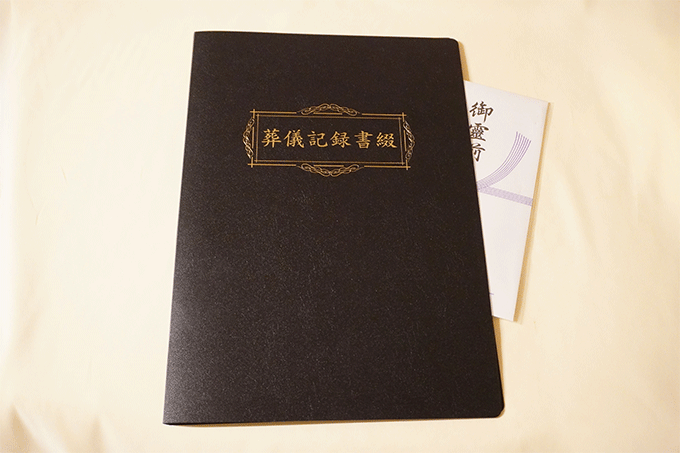
「明日はもっといい日になる」では、聴取者の方の「あなたのまちの冠婚葬祭・ある?ある!話」をご紹介しています。全国の様々な冠婚葬祭にまつわるご当地ルールはもちろん、「冠婚葬祭」の行事で起きたハプニングや出来事、マナーなどの質問でも構いません。冠婚葬祭を体験して「よかったなぁ」と思うことや、今では笑って話せるエピソードを添えていただけると有難いです。受付メールアドレスは ue@1242.com 。(※メールの件名は「冠婚葬祭」)
年末年始が近づくと、家族や地域とのつながりを考える機会は多いもの。改めて冠婚葬祭の大切さを再認識してみましょう。
【番組概要】
■番組タイトル『上柳昌彦 あさぼらけ』
■コーナータイトル:全日本冠婚葬祭互助協会 プレゼンツ 明日はもっといい日になる
■放送日時:毎週水曜 4時40分ごろ