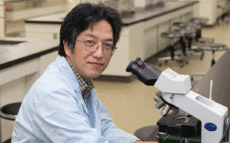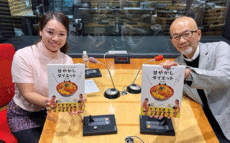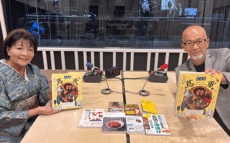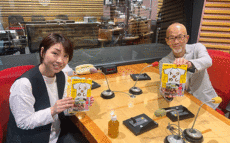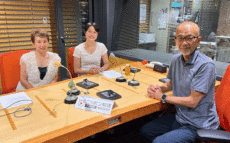いま日本のチーズが世界を魅了! 大絶賛される理由とは
公開: 更新:
NPO法人チーズプロフェッショナル協会会長の坂上あきさんが、上柳昌彦アナウンサーがパーソナリティを務める、ラジオ番組「上柳昌彦 あさぼらけ」内コーナー『食は生きる力 今朝も元気にいただきます』(ニッポン放送 毎週月・金曜 朝5時25分頃)にゲスト出演。チーズ好きが高じてこれまでおよそ1,000種類のチーズを食べ歩き、2023年からは協会の会長も務める坂上さんに、日本のチーズが世界で注目されている理由や、チーズの栄養や歴史など、チーズの魅力について聞いた。
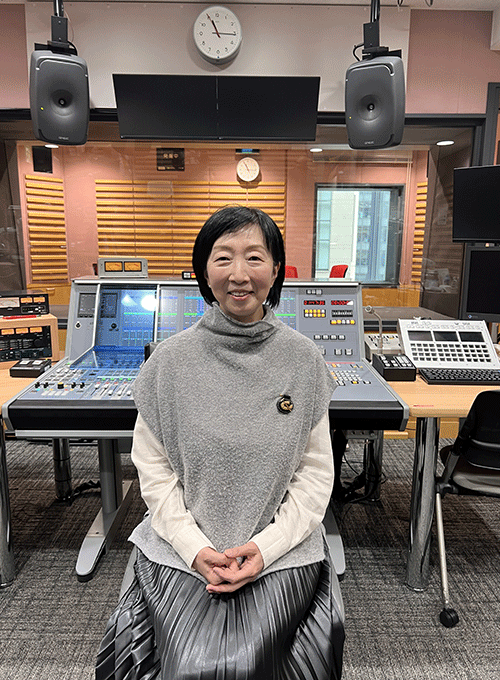
いま、日本のチーズが世界で注目されている
上柳:国際チーズコンテスト「ワールドチャンピオンシップ チーズコンテスト」(WCCC)というものがあって、最近は日本のチーズが大変高く評価をされているそうですね。
坂上さん:はい、WCCCで日本はナチュラルチーズでもプロセスチーズでも多く受賞しています。
日本でも、チーズプロフェッショナル協会がコンテストを開催していまして、そこで上位を取ったものを世界のコンクールに出品するサポートをしているのですが、持っていったものの半分ぐらいは受賞されたんです。
上柳:それはすごいですね!
坂上さん:はい、世界の人も本当にびっくりしていました。
上柳:みなさん、「なんで日本のチーズが?」と驚いていたのですか。
坂上さん:そうなんです、初めてコンテストにエントリーした時は、「日本でチーズなんか作っているの?」「日本って、牛を飼っているの?」ということも言われたりしたのですが、その最初の年にいきなり日本のチーズがベスト10に選ばれたんです。4000以上ものチーズの中から大変高い評価を得たので、世界の人たちがザワザワする……ということがありました。
上柳:日本の酪農業の方も一生懸命頑張っていますからね、海外の人にもぜひ知っていただきたいですよね。
坂上さん:チーズコンテストに出品するようになって5年ぐらいたちましたが、今は世界のチーズの専門家の方たちから、「日本のチーズはとても素晴らしいもの」というのが定着しています。
去年のコンテストでは「日本のミルクの質の高さが感じられる」と言われて、本当にうれしかったのを覚えています。もちろん、チーズ職人の方の技術もあるんですけれど、ミルクの品質の良さを分かっていただけたことも、感激しました。
上柳:酪農業の方の朝は早いし、そしてお休みのない仕事ですから。早朝のこの番組を聞いてくださっている方も多いので、自分が褒められたみたいでうれしいですね。
「ナチュラルチーズ」と「プロセスチーズ」の違い
上柳:先ほど、「ナチュラルチーズ」と「プロセスチーズ」があるとお話されていましたが、この2つは何が違うのですか?
坂上さん:プロセスチーズというのは、ナチュラルチーズを原料にしています。ナチュラルチーズを高温でドロドロに溶かし、溶かすと油が分離してしまうので、分離しないように乳化剤を添加します。これを冷やして固めたものが、プロセスチーズです。
一方、ナチュラルチーズというのは、生乳をいろんな微生物や乳酸菌、白カビ、青カビなどで発酵させ熟成させたものです。微生物が生きているので、置いておくとどんどん熟成して変化します。
上柳:なるほど。加熱して微生物が死んでしまうから、保存するためにはプロセスチーズが良いし、新鮮なうちに食べたり、味の変化を楽しんだりするなら、ナチュラルチーズがいいかもしれませんね。
坂上さん:日本には乳文化というものがほとんど無かったので、ヨーロッパなどの伝統的なチーズ文化とはまったく違う発展をしてきました。
飛鳥時代にチーズが入ってきたことがあったんですが、それは一部の高貴な人たちのお薬のような存在でした。栄養があるもの、ということで。その後は廃れてしまいました。
本格的に入ってきたのは江戸時代で、多くの人に食べられるようになったのは戦後です。戦後の日本人の栄養状態が悪い人たちに向けて、アメリカがプロセスチーズを持ってきました。
上柳:給食で脱脂粉乳などが出されていた頃ですね。そのプロセスチーズですが、日本のものは相当おいしいらしいですね。
坂上さん:そうなんです。日本の各大手メーカーさんが、プロセスチーズをいかにおいしくするかということに力を注いでいますが、世界では本当に珍しいことです。海外に行ってプロセスチーズを食べていただいたら分かりますが、あまり味がしません。『日本のプロセスチーズはなんておいしいんだ!』と思うはずです。
「たんぱく質」「脂肪」「カルシウム」が豊富
上柳:チーズには、定義みたいなものはあるのですか?
坂上さん:ミルクを固め、そこから水分を抜いたものが「チーズ」と定義されています。
上柳:牛乳はほとんど水分ですよね?
坂上さん:そうですね。90%が水分で、水を抜いた残りの10%が栄養になるところです。なので、牛乳の栄養をぎゅっと凝縮したものがチーズ、という風に考えることもできます。
上柳:「牛乳といえばカルシウム」とよく言いますが、チーズにはどんな栄養が含まれているのですか?
坂上さん:チーズの栄養は、「たんぱく質」「脂肪」「カルシウム」が主要な部分を占めています。
上柳:人間の体にとって大切な栄養ばかりですよね。
坂上さん:赤ちゃんは離乳するまでの間、ミルクだけで育ちますから非常に栄養価が高いです。しかも、赤ちゃんが食べられるくらい消化がいいので、とても体にいいものです。
上柳:そんな体にいいものを、水分を抜いてギュっと固めたものですから、きっと栄養面でも満点なのでしょうね。
チーズの歴史
上柳:チーズの歴史についてですが、いつ頃にどんな形で作られたのでしょうか。
坂上さん:紀元前に、メソポタミア文明の発達した中東のチグリス・ユーフラテス川のあたりで、ヤギや羊を飼うことが始まったとされています。牛と違って、ヤギや羊は小さいし人懐っこいし、群れる性質もあるので飼いやすかったのだと思います。
飼っているうちに羊に子どもが生まれ、お乳を飲んで育つのを見て、何かのきっかけで人間もミルクを飲むようになりました。絞ったミルクは、自然にある乳酸菌で発酵が始まるので、「この塊も食べられるし、おいしい」となったようです。
上柳:空気中に漂っている乳酸菌と結合して、自然とミルクが発酵して固まり、食べてみたらおいしかったのですね。
坂上さん:しかも、水を抜いた方が保存性も高まります。
上柳:水を抜けば抜くほど長く持つし、保存食になると気づいたのですね。
坂上さん:はい、これがチーズの始まりだと言われています。
上柳:いま、世界にはどれぐらいの種類のチーズがあるんですか?
坂上さん:いつも回答に困ってしまう質問なのですが、1万ぐらいはあると考えているので「星の数ほどある」と答えています。ヨーロッパには白カビや青カビのチーズがあるし、モンゴルに行けば乾燥したカチカチのものがあるなど、世界にはいろんなチーズがあります。
上柳:ちょっとした村で独自のものを作っていたり、我が家のチーズといったものもあるでしょうね。
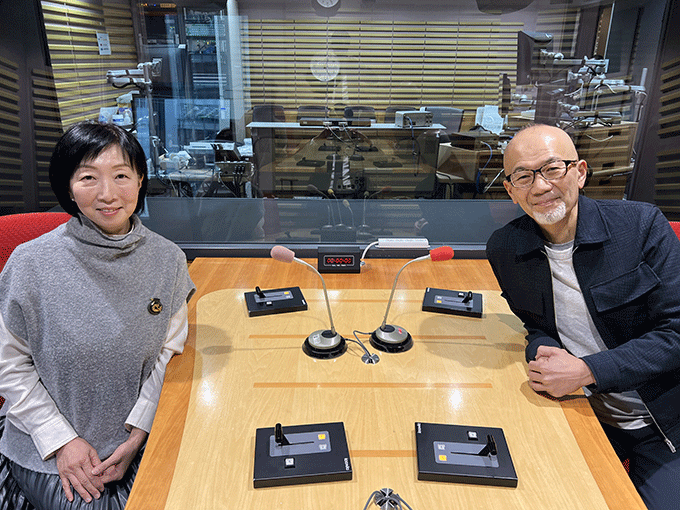
――日本のチーズは今、世界からも高く評価される存在となった。そこには、日本の豊かな自然と清らかな水、チーズ職人の細やかな技術、品質の高い牛乳を生産するための酪農家の尽力が反映されている。ぜひ一度手に取って、国産チーズの豊かな味わいを体験してみてはいかがだろうか。
NPO法人チーズプロフェッショナル協会会長・坂上あきさんと、上柳昌彦アナウンサーの詳しいトーク内容は、「食は生きる力今朝も元気にいただきます」特設コーナーHP(https://www.1242.com/genki/index.html)から、いつでも聞くことが可能だ。
番組情報
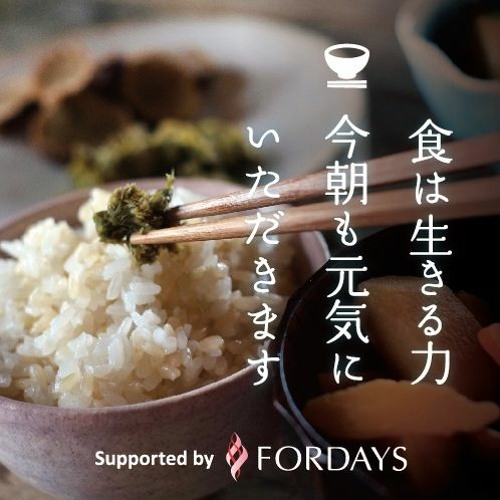
「上柳昌彦 あさぼらけ」内で放送中。“食”の重要性を再認識し、「食でつくる健康」を追求し、食が持つ意味を考え、人生を楽しむためのより良い「食べもの」や「食事」の在り方を毎月それらに関わるエキスパートの方をお招きしお話をお伺い致します。
食の研究会HP:https://food.fordays.jp/