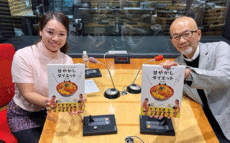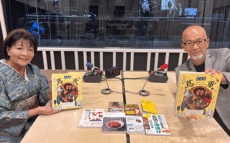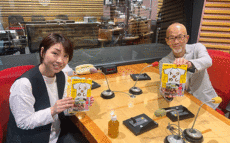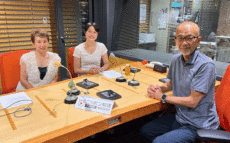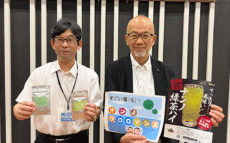滋賀医科大学医学部准教授でコーヒー研究者の旦部幸博さんが、上柳昌彦アナウンサーがパーソナリティを務める、ラジオ番組「上柳昌彦 あさぼらけ」内コーナー『食は生きる力 今朝も元気にいただきます』(ニッポン放送 毎週月・金曜 朝5時25分頃)にゲスト出演。『コーヒーの科学「おいしさ」はどこで生まれるのか』(講談社ブルーバックス)や『珈琲の世界史』(講談社現代新書)の著者である旦部さんに、ブルーマウンテンやコーヒーハウスなどの歴史、コーヒーの飲み方の変化などについて聞いた。

「ブルーマウンテン」の評価が高いワケ
上柳:コーヒーといっても「ブルーマウンテン」とか「ジャマイカ」とか、最近では「ゲイシャ」など、いろんな種類がありますよね。旦部先生はなにか好きなコーヒーがあるのですか?
旦部先生:基本はなんでも好きで飲みますが、昔から好きな銘柄としては「マンデリン」です。このマンデリンは、インドネシア・スマトラ島の北部でとれるコーヒーで、味は割と深入りで、昔の喫茶店でよく出されていました。
上柳:なるほど。私は「ブルーマウンテン」と聞くと、どうしても『おおっ、凄そうだな、高級そうだな』と思うのですが、実際はどんな豆なのでしょう?
旦部先生:もともと、ブルーマウンテンは20世紀初頭ぐらいから、海外で非常に高く評価されていました。アメリカで書かれた『オール・アバウト・コーヒー』というコーヒーのバイブルと呼ばれているような、ちょっと古い本があり、この中で高く評価されています。
それを見た日本の商社の方が、『世界にはこういう豆があるんだな』ということで、日本に持ち込みました。ただそのときに日本の輸入業者は、ブルーマウンテンがイギリス領でとれていたというだけで、「英国王室御用達」というキャッチフレーズをつけてしまいました。御用達だったのか、実際は分からないんですけれども……。
上柳:「イギリス領のコーヒーだから、英国王室もたぶん飲んでいるよね~」という話だったと?(笑)
旦部先生:はい。けっこういい加減だったようですが、しっかりブランドイメージはついたわけです。
上柳:たしかに、「英国王室御用達」と言われたらありがたい感じがしますね。
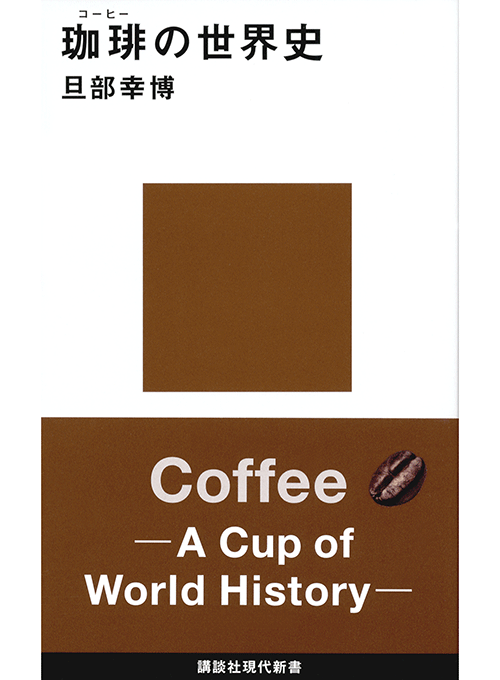
イギリスで起きたコーヒーブーム
上柳:イギリスというと「紅茶文化」のイメージがとても強いのですが、コーヒーの文化もあったということですか?
旦部先生:実はコーヒーの方が先で、17世紀の半ばぐらいのイギリスでは「コーヒーハウス」というものが大流行しました。
上柳:コーヒーハウスは本にもよく登場しますよね。名前の通りコーヒーを飲むために集まる場所で、でも当時は女性が入れなくて揉めたりとか。そういう場所が本当にあったんですね。
旦部先生:はい、コーヒーハウスはいわゆる喫茶店の起源です。
あの当時のイギリスは、貴族社会から市民社会に変わった市民革命があった時代です。貴族たちにはサロンがあったので、そこに集まっていろいろと密談したりしていましたが、市民にはそういう場所がありませんでした。
その時にちょうどコーヒーが入ってきたわけです。もともと、イスラムの方では「カフェハネ」というコーヒーハウスのようなものがあったので、それをそのままイギリスで取り入れ、ロンドンなどでコーヒーハウスという形で開かれました。
すると、それがちょうど時代にマッチし、コーヒーハウスは大流行を起こすんです。もう、なんでもかんでもコーヒーハウスで話し合われました。
上柳:コーヒーを飲みながら政治の議論をしたり、近所のうわさ話をしたり、皆さんが集まってワイワイしていたと。
旦部先生:そうですね、商談なども全部コーヒーハウスで行われていたので、社会のすべてが集約されていたような場所だったようです。
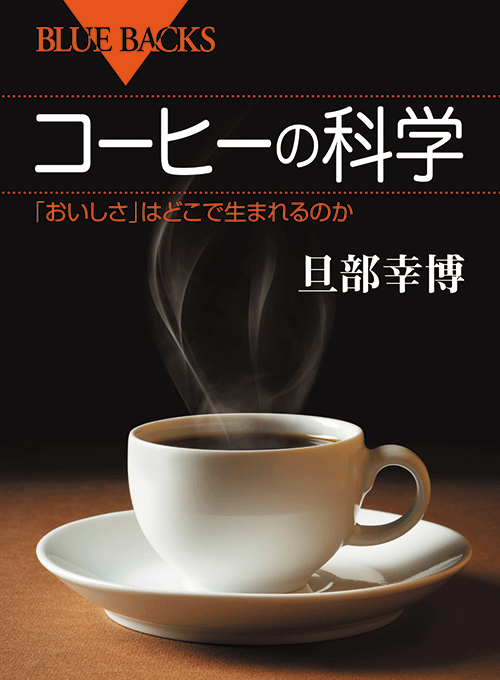
コーヒーのおいしさは鮮度で変わる
上柳:おいしいコーヒーを飲むための、ワンポイントアドバイスがあれば教えてください。
旦部先生:豆で買って、コーヒーを飲む直前に豆を引くというのが一番いいと思います。
上柳:私はいつも、既に引いてある豆を買ってくるんですが、ちょっとでもおいしく飲める方法はありますか?
旦部先生:コーヒーは日持ちしますが、時間が経つとやっぱり香りが抜けてしまうので、できるだけ早く飲み切るといいと思います。豆を密封された容器に入れ、冷蔵庫に保管するというのも悪くはないですが、先延ばしするための方法です。コーヒーがお好きな方は、早めに飲むことをおすすめします。
上柳:コーヒーを飲むとカフェインで覚醒作用や眠くならない効果がありますが、こうした効果が“コーヒー伝説”みたいなものを生んだそうですね。
旦部先生:コーヒーをヨーロッパに持ち込んだ会社が、宣伝のために広めた逸話がたくさんありますね。中でも一番知られているのは、カルディコーヒーファームでも知られる、カルディです。
上柳:駅前の商業施設にある、あのカルディですか?
旦部先生:はい。「カルディ」というのは、コーヒー伝説に出てくるヤギ飼いの少年の名前です。その少年が飼っていたヤギが、夜中に騒いでいてどうも様子がおかしいと。それで調べてみたら、ヤギが赤い実を食べていて、少年も赤い実を食べたらなんだか心がウキウキして、ヤギと一緒に踊った……みたいな(笑)。そして、それがコーヒー豆の発見に繋がったという伝説です。
この話は世界的にも広がっているので、「これが真実だ」と捉えている人が多くいるのですが、これはおとぎ話ですね。
昔は違う飲み方だった
上柳:コーヒーはどんな所で栽培されているのでしょうか?
旦部先生:現在は世界中の赤道付近です。南回帰線と北回帰線の間ぐらいが、「コーヒーゾーン」と呼ばれており、その辺りで栽培されています。
熱帯地方なので熱いところで育つと思われがちなんですが、標高の高いエリアで栽培されます。大体標高800メートルから1500メートルぐらい。2000メートルぐらいまでいけるかもしれません。平均気温は大体15度から25度ぐらいなので、私たちにとっても非常に快適な、年中通してそういう気温の所で育つ植物です。
上柳:イメージ的には、太陽の光が照りつけて、気温の高いところで育つのだろうと思っていました。コーヒーの飲み方は、昔と今では違うのでしょうか?
旦部先生:最初の頃は飲み方が違ったようです。コーヒーノキには「コーヒーベリー」とか「コーヒーチェリー」と呼ばれる真っ赤な果実ができて、その中にある大きな種がコーヒー豆の元になる「生豆」です。私たちが飲んでいるコーヒーは、この生豆を炒って飲みます。
でも最初の頃は、果実をカラッカラに乾燥させて丸ごと炒って使ったり、逆に、種を捨てて果肉だけを炒ってフルーツティーのように飲んだりしていたようです。ですから、最初の頃から焙煎は行われており、お茶と一緒で、保存性を高めるために火入れをしていたのです。


――コーヒーの歴史を振り返ると、その一杯にはさまざまな物語があり、昔から人々を惹きつけてきたことがわかる。そんな奥深い背景に思いを馳せながらコーヒーを味わえば、より一層おいしさを感じたり、新しい発見があるかもしれない。
滋賀医科大学医学部准教授でコーヒー研究者の旦部幸博さんと、上柳昌彦アナウンサーの詳しいトーク内容は、「食は生きる力今朝も元気にいただきます」特設コーナーHP(https://www.1242.com/genki/index.html)から、いつでも聞くことが可能だ。
番組情報
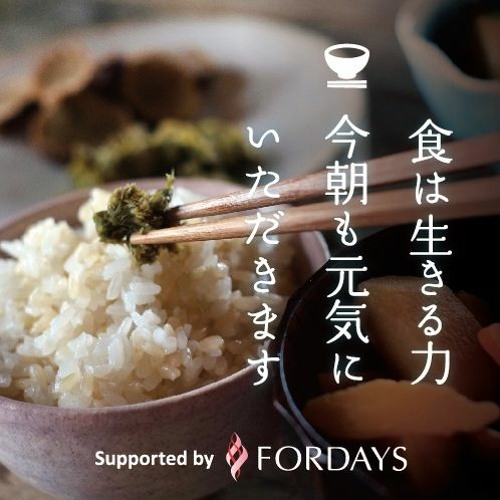
「上柳昌彦 あさぼらけ」内で放送中。“食”の重要性を再認識し、「食でつくる健康」を追求し、食が持つ意味を考え、人生を楽しむためのより良い「食べもの」や「食事」の在り方を毎月それらに関わるエキスパートの方をお招きしお話をお伺い致します。
食の研究会HP:https://food.fordays.jp/