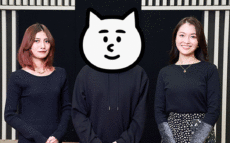『スルミ presents トップジャム』は、ビジネスのトップシーンで活躍する方や、気になる時事問題を読み解くスペシャリストをゲストに迎えて、素顔に迫る番組です。
本日のゲストは、映画監督で作家の森達也さんです。森さんは、映画『FAKE』『福田村事件』など社会性のある話題を題材として撮影してきました。
全作品を観ているという大ファンの石塚さん。きょうは少しテンション高めかもしれません!?
さて、どんなお話が飛び出すでしょうか。
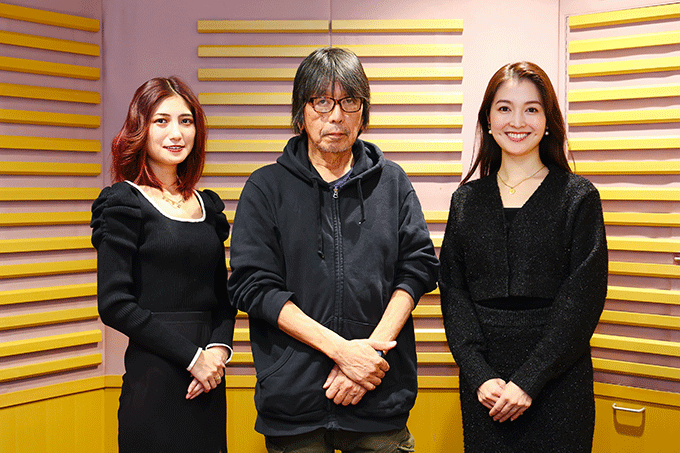
福田:いろいろとお話を伺っていければと思います。まずはプロフィールをご紹介しましょう。
森達也さんは、広島県のご出身。1992年、テレビのドキュメンタリー番組『ミゼットプロレス伝説 〜小さな巨人たち〜』でデビュー。オウム真理教信者に密着したドキュメンタリー映画『A』、続編となる『A2』などを制作。初の劇場映画『福田村事件』は一昨年公開され、第47回日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞。大きな話題を呼びました。作家としては、『千代田区一番一号のラビリンス』など執筆されています。
石塚:森さんって、オウムの信者側や佐村河内さん、どちらかというと社会からバッシングされている側を撮られるなと思うんですけども、わざわざそこを被写体として選ぶ理由は何でしょうか?
森:まず、オウムの側あるいは佐村河内さんの側でもあたりまえのことで、例えば、中学生のドキュメンタリーを撮ろうと思ったら、その中学生の通っている学校に行って授業の様子を撮ったり、家庭に行ったり。あたりまえですよね。だから、そのあたりまえのことをオウムの場合でも佐村河内さんの場合でもやっただけなんです。要するに、他の誰もそれをやらないので、僕の作品だけはちょっと目立ってしまうっていう、そういう感じですよ。
石塚:ダイレクトにアタックしていいですよ、って返事が来たってことですよね。ちょうどオウムも一番渦中の時に撮られてたと思うんですけど。

森:ほぼ二つ返事でしたけど、あの時期にオウムにオファーすれば誰でも撮れたんです。でも誰もしなかった。
福田:メディアに携わってる人間としては、なんか触れるのが難しそう、触れてはいけないものと思えてしまうところもあるんですけれども、そこは真髄に迫りたいとアプローチされたんですか?
森:当時、テレビのディレクターでしたけど、とにかく早朝から夜中までオウムの特番だらけみたいな時期で、オウム以外の企画は全然通らないんですよ。そういう時期だったので、じゃあ自分はドキュメンタリーを撮ってるから、ドキュメンタリーの手法であれば、オウムの信者たちを撮るしかないよなと思って。連絡して「撮っていいですか?」って聞いたら「いいですよ」と。だから自分としては自然な流れなんですけど、気がついたら周りにメディアの人が誰もいない。
石塚:森さんの作品を見ているとあくまで中立なんですよね。どっち側に立つこともなく、ただ淡々と中立に物事を見ていく。どういう手法で中立を保てるんですか?
森:中立は全然意識してません。意識せずにむしろ自分の感覚。主観ですね。中立ってそもそも無理なんですよ。つまり、A点とB点の間に、等距離AからもBからも等距離のC点。これが中立だともし定義するんであればA点とB点、誰が決めるんですかって話になるわけで、絶対にそこには主観が入ってくるんです。だから客観的な中立っていうのは、僕は幻想でしかないと思っているので、そこには立脚しないし、意識もしません。ただ、自分の感覚には正直でありたいと思っていて、結果的にはそれが中立に見えちゃうんでしょうね。
福田:ちなみに、なんで皆さんは触れられなかったと思いますか?
森:オウムと交渉してはいけないみたいなね。絶対的な悪だけど、撮るためには話し合いや、こうしましょう、ああしましょうってネゴシエーションしなきゃいけないってことが、その段階でメディアとしてやっちゃいけないみたいな無意識な縛りみたいなものがあったのかなって。ちょっと僕にはわからない。
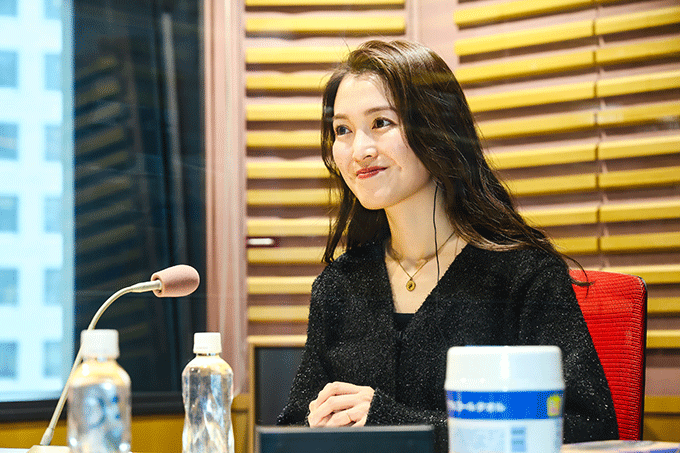
福田:今の時代だと、なおのことできない気がするんですけど、そのあたりはどうお考えですか?
森:オウムの事件、もう30年前ですよね。あれをきっかけにして、社会とメディアはずいぶん変わったなと思ってます。変わったっていうのは、もちろん良い方向じゃないですね。より悪い方向に、加速度的に変わってきたと思ってるんで。だからいろんなタブーや自粛規制、忖度
が増えてきたり同調圧力が強くなったり。そういう傾向は今の方が強いかもしれないですね。ってことはやっぱり、メディアも自由に呼吸ができなくなってる。
「(メディアが)会社」になっちゃってるんですよね。もちろん前から会社ですし、会社は社会を構成する重要な因子なんですけれど、メディアってやっぱりちょっと違うと思うんですよ、普通の企業とはね。つまり売り上げだけではなくて、そこにジャーナリズムって縦軸も入ってくるし、これって市場原理とは相容れない。つまり、みんなが喜ぶもの好むものばかりを提供していたら、ジャーナリズムは崩壊しますよね。だからそこは企業としては無理なんですよ。
ドキュメンタリーも同じで、テレビもほとんど衰退してますけど、視聴率も取れないし結構リスクが大きい、ドキュメンタリーの場合はね。肖像権とかいろんなところに引っかかる可能性もあるし。テレビ局も企業化して、コンプライアンス、ガバナンス、リスクヘッジ……、こういった言葉ばかりが強くなって、そうするとやっぱりドキュメンタリーって効率悪いんですよ。
だから、みんなそうしたものをどんどん避けてしまう。結果としてはメディア全般、そしてジャーナリズムも、この国ではどんどん衰退してしまっていくっていうことになるんじゃないかな。

石塚:以前はテレビのドキュメンタリーを作られていたと思うんですけれど、何をもってお辞めになられて、今の立場になられたんですか?
森:「A」というオウムのドキュメンタリーを撮っている過程で、所属していた制作会社をクビになったんですよ。デジカメは出はじめでしたけど自分で用意して、一人でオウムの施設に通ってたらそれがバレて。危険な動きをしてるから、こいつはもうクビにしろと。
福田:そういったことが起こり得るから、皆さんきっと手を出せなかったと思うんですけど。それでも森さんはお一人で撮り続けたわけですよね。
森:そう言うとなんかすごく信念が強いに見えるでしょう。そうじゃなくてね、甘く見てたんですね。クビにはならないだろうと思っていたし、他のどこか持っていけばやってくれるかなと。でも全部ダメで。映像見た瞬間にこんなの放送できませんって言われて、そのあたりでテレビでは無理だなと諦めたんですね。じゃあ、もう映画しかないかって。
福田:森さんが発信されていることはとても勇気があることだと私は思うんですけれども、そういった真髄にあるところの気持ちや大切にしていることがあれば教えてください。
森:前提が違うんですよ。僕、勇気、特に強くないですよ。鈍いんです。鈍いから、周りがみんなこれは触っちゃダメとか言ってるのに、「え、どれ」って言ってパッと触っちゃったりして。でもね、経験則でみんながこれは触ったら火傷するとか言ってるものが、火傷しないものが多い
ってことはなんとなく知ってるんで。鈍さに経験が重なったというか。だから、そういう意味ではあんまり恐れずに行ってるから、勇気があるようにもしくはモチベーションが強いとか信念があるとかふうに見られがちなんですけど。全然違います。もう本当単に鈍いだけですよ。
福田:そうすると、触れてみるっていうことがまずは大事なんですかね。
森:メディアにもそれは言えますよね。タブーが多すぎるというか、自分たちで自爆自浄してるわけですから。やっちゃえばいいんですよ。でも誰もできないみたいなね。
これは特にオウム以降、同調圧力も強くなってるし誰もやらないからやらない、みたいな感じになっちゃってるんでしょうし。誰かが誰かを叩いたら、みんなで群がって叩くみたいなことにもつながっているし。そういう傾向には、やっぱりメディアがもっと抗った方がいいんじゃないかなと思います。