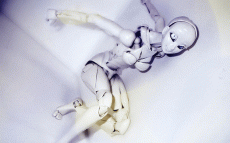5月14日、大阪・なんばのシネコンで、ある日本映画が公開されました。
タイトルは『あのひと』。
新作なのにモノクロ、しかも基本的に一発撮りで撮影されたこの作品、
監督を務めたのは、山本一郎さん・52歳。
これが初監督の山本さん、普段は映画会社・松竹のメディア事業部に勤めるサラリーマンです。
しかしこの映画は、別に会社が資金を出して撮らせてくれたわけではありません。
撮影所は借りましたが、山本さんが自分の貯金を崩して撮った“自主製作映画”なんです。
大阪生まれの山本さん。京都大学を卒業後、映画監督を志し、京都・太秦の松竹撮影所内に開校された「KYOTO映画塾」に参加。
それがきっかけとなり松竹に入社しました。
昔と違って今は、社員が映画監督になるケースは極めて稀で、山本さんも5年前まで、10年以上にわたって現場の仕事をしていましたが、役職はあくまで「プロデューサー」。
山田洋次監督の『たそがれ清兵衛』や『武士の一分』にもプロデューサーとして関わり、作品のヒットにも貢献しましたが、
「いつか自分の手で映画を撮れたらなあ…」
という気持ちが心のどこかにずっとあり、現場を離れたことで、よりその気持ちは強くなりました。
4年前、山本さんはある新聞記事を目にします。
大阪の中之島図書館で、「作者不詳」として所蔵されていた未発表の古い映画脚本が、専門家の調査によって、大阪を代表する作家・織田作之助の作品と認定されたというのです。
大阪出身で、織田作之助が好きな山本さんは「これは、自分の目で見ておかないと」と思い、休みを利用して大阪へ。知人たちと4人で中之島図書館へ向かい、幻の脚本を一緒に閲覧しました。
「表紙の『あのひと』というタイトルの左下に、『松竹映画大船作品』とあって、ハッとしたんです。そうか、松竹で撮るはずだったんや…。不思議な縁を感じましたね」
太平洋戦争末期の、昭和19年に書かれた『あのひと』。戦死した上官の遺児を育てる帰還兵。
同じ街に住み、男たちよりも闊達(かったつ)に生きる若い娘たち・・・戦時中に懸命に生きる様々な人たちを描くことで、戦時中の重苦しい雰囲気を嫌い戦争自体に疑問を感じている織田作之助の思いも伝わってきました。
おそらく、検閲に引っ掛かってお蔵入りになったこの脚本を、いま自分の手で映画にしてみよう!
山本さんは、さっそく会社に映画化を提案しましたが、答はノーでした。
「やっぱりアカンかったか…。」
悶々とする中、リフレッシュ休暇の知らせが届きます。
「待てよ、夏休みと合わせると2週間ぐらい休める。一本撮れるんちゃうか?」
夢を実現する最後のチャンス。こうなったら、前に進むしかない…。山本さんは、入社以来コツコツ貯めていた貯金500万円を崩して、『あのひと』を映画化しようと決意します。
会社はノータッチですが、一緒に図書館へ脚本を見に行った知人たちを中心に、プロデューサー時代、一緒に仕事をした腕利きのスタッフたちも、続々と参加してくれました。
役者も、山田洋次作品で関わった神部浩さん、田畑智子さんほか、実力派の俳優が集結。話を聞きつけた山田洋次監督も、そっとカンパを寄せてくれました。



かつて山本さんが映画を学んだ、太秦(うずまさ)の松竹京都撮影所で2013年夏にクランクイン。
脚本が書かれた昭和19年の空気感を再現するため、山本さんはあえて、当時の主流だったモノクロ・スタンダードサイズで撮影。
さらに、戦時中はフィルムが貴重品だったためすべてワンテイクで撮影していたと仮定して、この作品も基本的に「一発撮り」で進め、慣れない部分は多々ありましたが、準備1週間、撮影1週間で、全ての内容を撮り終えました。
休日を使って編集を行い、ついに『あのひと』は完成。長い間、日の目を見なかった脚本が、70年の時を超えて蘇ったのです。

日本での公開前に、去年の11月、ベラルーシで行われた「ミンスク国際映画祭」へ『あのひと』を出品したところ、山本さんは、二度も壇上に上がることになりました。
映画祭では異例の「二つの特別賞」を受賞したからです。
一つは「映画を信じることの奇蹟、人生を信じることの奇蹟への特別賞」。
そしてもう一つは「日本映画の伝統へのこだわりに対しての特別賞」。
山本さんは、こう言います。
「旅費も宿泊費も、全部自腹ですから、またおカネが出ていったんですけどね(笑)。でも、二つの賞状を見ていると、つらいことは全部吹き飛んでいきます。この作品が評価されて、関わってくれた方々の評価につながったら嬉しいです」