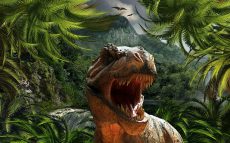水筒のめくるめく歴史
公開: 更新:

日本での水筒の歴史
ひょうたんや竹の水筒
古くから日本では『ひょうたん』や『竹』で出来た水筒が使われてきました。
それが江戸時代になると、そうした水筒に漆を塗ったり、家紋を入れたりして、オシャレになっていきました。
それをお芝居の見学や、お花見などに行く時に持ち歩いたそうです。
アルミ製の水筒
兵隊が戦地で使うために作られた
その後、1897年(明治30年)頃になると『アルミ製の水筒』が登場します。
同じ『アルミ製の水筒』でも、フタの部分に“方位磁石”が付いたものがあったそうです。
これは兵隊さんが戦地で使うために作られたもので、そのために方位磁石が付いていました。
さらに、その水筒には皮の紐が付いていて、肩から斜めに掛けられるようになっていました。
当時、『アルミ製の水筒』は軍事用の工場で作られていたそうです。
そのため、こうした兵隊さん用の水筒も作られていたというわけです。
プラスチック製やステンレス製が登場
戦後になると、水筒の世界は大きく変化します。
『プラスチック製』や『ステンレス製』などの水筒が、次々と登場しました。
ガラス製の魔法瓶の水筒
さらに昭和30年代になると、『魔法瓶』が普及するようになって、『ガラス製の魔法瓶の水筒』も登場しました。
『プラスチック製の水筒』の場合、持ち歩いているうちに中の飲み物が、ぬるくなってしまう欠点がありました。
また『ガラス製の魔法瓶の水筒』は衝撃に弱かったので、すぐに割れてしまって、イザ飲もうとした時、中身がグシャグシャになることも少なくありませんでした。
こうした欠点を解消しながら、水筒は進化していきました。
(2017/9/12放送分より)
ニッポン放送ほか全国ネット
FM93AM1242ニッポン放送 月~金 朝7:37から(「高嶋ひでたけのあさラジ!」内)
※ネット局の放送時間は各放送局のホームページでお確かめください。