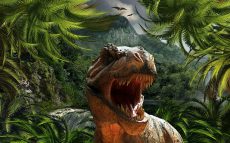紀元前3,000年から使われていた水筒
公開: 更新:

水筒の歴史
水筒の誕生
水は人が生きていくためには、欠かすことが出来ません。その水を蓄えておくための容器が、古くから次々と考え出されました。
その中でも“水を持ち歩くための容器”として“軽くて持ち運びやすいモノ”は何なのか?考えられていました。
最初は動物の皮でできていた
その中から生まれたのが『水筒』で、紀元前3,000年頃には既にヨーロッパや中国で使われていたそうです。
当時の水筒は“動物の皮を加工して、袋状に縫い合わせたもの”でした。
なぜ水や酒をひょうたんに入れた?
それ以外にも、よく利用されていたのが『ひょうたん(瓢箪)』です。
ウリ科の植物で、アフリカが原産地と言われていますが、日本には紀元前の縄文時代に伝わったとされています。
その『ひょうたん』の実から、果肉の部分を取り除いて乾燥させたものを容器として使いました。『ひょうたん』は成熟すると、実の皮の部分がとても固くなることから、お水やお酒の容器としてピッタリでした。
さらに『ひょうたん』の皮には、とても細かい穴がいくつもあってそこから気化熱が奪われることから、中のお水の温度が上がりにくかったそうです。まさに現在の魔法瓶のような効果があった・・ということです。
日本で『竹筒』がよく使われていたワケ
加工が簡単
そんな『ひょうたん』と同じように、日本でよく使われていたのが『竹筒』です。
竹筒の片方に穴を開けて、その中にお水を入れます。
竹は中が空洞になっているのと、加工が簡単です。
さらに日本の竹は小ぶりで、持ち運びにちょうど良かったので水筒には最適でした。
この『竹筒の水筒』が、現在の水筒の原型だそうです。
(2017/9/11放送分より)
ニッポン放送ほか全国ネット
FM93AM1242ニッポン放送 月~金 朝7:37から(「高嶋ひでたけのあさラジ!」内)
※ネット局の放送時間は各放送局のホームページでお確かめください。