フリーアナウンサーの柿崎元子による、メディアとコミュニケーションを中心とするコラム「メディアリテラシー」。今回は、コミュニケーションで大切にしていることについて---

ニッポン放送 NEWS ONLINE
スポーツイベントやコンサートなどの、中止や延期が相次いでいます。新型コロナウイルス感染が爆発的に広がり、人が集まることはもちろん、外出自体を自粛するようになりました。
不安と焦りに耐えながら憂鬱な日々が続きます。そうしたなか、学生時代にとてもお世話になったO先生が定年を迎え、大学を去ることになりました。最終の講義は2月下旬。その後に懇親会を開き、O先生をねぎらうとともに、次のステージをお祝いする計画です。
学生時代の仲間が、学年を超えて大勢集まることになりました。連日徹夜した試験、辛かったレポート、脂汗が出た授業中の指名など、さまざまな思い出話に花が咲く…はずでした。しかし、世界的に猛威を振るう新型コロナウイルスを前にしては、やはり中止せざるを得ませんでした。
O先生ご自身も残念に思われていることと思います。先生は学者らしく、適格に、正確に事象や感情を表す言葉を発する方で、冷徹な人にも見えました。私たちが多用する「~な感じ」や「~みたいな」「~的」などのあいまいな言葉は使いません。
野球に例えると、直球を次々と投げて来るような話し方でした。きついなと感じる一言もありました。しかし、実際は多くの学生から慕われていました。なぜ慕われたのでしょうか?

ニッポン放送 NEWS ONLINE
【人は恵まれていることに気づかない】
O先生は優しく、思慮深く、学生1人1人に大事な言葉を投げかけてくれていました。私には、「人は恵まれていることに気づかない」と話されました。
例えば、健康な人が病気になると「健康って大事だな」と感じます。日ごろ健康であることは、自分のなかで当たり前なので気づきません。具合が悪くなって、はじめて健康であることに感謝します。人は恵まれていることに気づかないのです。
また、よい“健康状態”を保つために、それなりに努力はします。ただ、どうあれば健康なのか、その到達点は人それぞれです。到達してもしなくても、誰かにとがめられるものでもありません。このファジーな感じが、当たり前化に結びついているのかもしれません。
「あの人のように頭がよかったら」「彼女のようにスタイルがよかったら」「彼のような大企業の社員だったら」など、私はいつも自分の状態を誰かと比較してうらやましがっていました。これに対してO先生はこう話されました。
「君は十分恵まれている。それに気づきなさい。そして感謝しなさい」

ニッポン放送 NEWS ONLINE
【自分の当たり前を疑え】
自分の現状を振り返るには、とても大事な言葉でした。そして自分に目を向けると、考えが独りよがりに凝縮してしまうため、先生はこう話されます。自分の当たり前を疑えと。
最近、お菓子のCMでもマツコさんがこうコメントして、ちょっとしたはやり言葉になっています。自分の当たり前を疑うというのは、自然にわかっていることでも、相手にとってはそうでないものがあるということです。例えば普段、話している会話を見直してみましょう。
『このタスクのソリューションを見つけることが、プライオリティーナンバーワンです。その際にエビデンスを求めたいと思います。なる早でおねがいします』
IT企業で働いていると聞こえて来そうな会話です。「いやいや、こんな会話しないよ~」とおっしゃる方もいるでしょう。それらしい単語を並べすぎたかもしれません。では、以下はどうでしょうか?
『完パケの尺は3分、FDさんに伝えといて。その後は生読みだからナレ原がサブに渡っているか確認、あと演者さんの位置バミっといて。演者さんがハケたら教えてね』
メディアではこのような単語が飛び交います。なぜかわかりませんが、用語を省略することが多いのです。専門的な言葉はわかりにくいのに、それを短くするとさらにわかりにくくなりますね。
完パケ=完全パッケージ、FD=フロアディレクター、ナレ原=ナレーション原稿などは、音の響きがいいという理由だけで短くしたのではないかと考えています。いずれにしても自分にとって当たり前となっている言葉が、相手にはそうでないこともあるので、十分に説明が必要です。学者は当たり前を疑うことから研究が始まるのかもしれません。
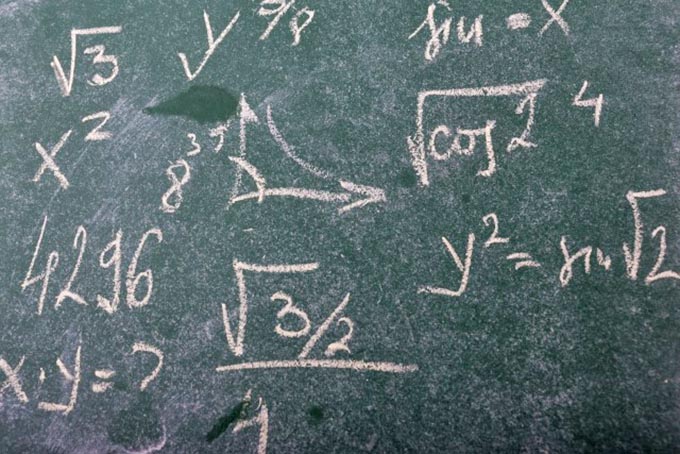
ニッポン放送 NEWS ONLINE
【たとえ話の効果】
O先生の専門である金融は、数式や難解な用語が多いため難しいというイメージが持たれています。しかし、授業は金融にくわしくない人にもよくわかると評判でした。先生はなぜ、難しいことをわかりやすく伝えることができたのでしょうか?
それは、“たとえ話の多さ”です。授業で聞いている人に合わせて、多くの事例を繰り出すのです。
男子学生Aくんと、近くに座っている女子学生Bさんを指し、「AくんはBさんに恋愛感情をもっているか?」と聞きます。Aくんは「意識したことがない」と返事をします。「君はこの美しいBさんを意識しないのか!」などと笑いをとりながら、「意識していない意識は不確実なものだが、それはどうでもよい、君には何の影響もないよな。ただそれだけのことだ」と言います。
そして、「あるときから君がBさんを意識しはじめたとしよう。すると彼女がいま何をしているか、きょうは何の授業に出るのか、さっき一緒にいた男は誰だ? と、すべてが重要な関心事になるだろう。そうなったときにリスクという概念が生じるのだ。そういうものなのだ」と力説します。
私が金融概念の重要なことを理解したかは別として、このような身近な事例は、確かに頭に残ります。O先生は授業にまったく関係ない話をしているようで、実は重要なことを説明していて、それが秀逸でした。
このように相手に伝えるためには、さまざまな事例を挙げること。O先生は事例の引き出しを、本当にたくさんお持ちでした。
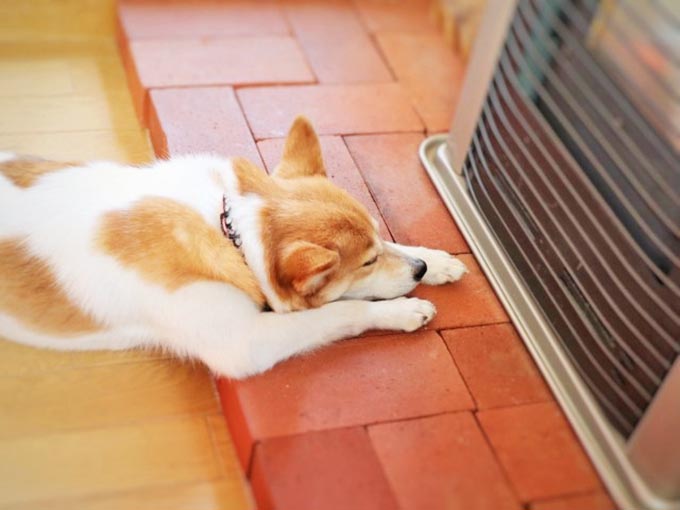
ニッポン放送 NEWS ONLINE
【よい結果がもたらされる】
O先生の退官にあたり、思い出となったことをつらつら書き記しましたが、つまるところ「君は恵まれている。それを意識した上で物事を考えれば、おのずと見えて来るものがある。これまで見えていなかったことに気づき、それを踏まえて当たり前を疑い、常に相手のことを考えながら行動することで、必ずよい結果がもたらされる。だからしっかりやりなさい」……そう言われたような気がします。
2020年になり、桜の季節を迎えましたが、この数ヵ月で世界は激変しました。マイナスの出来事しか起きていないように感じますが、このようなときだからこそ、できることを前向きにやって行こうと思います。(了)
連載情報

柿崎元子のメディアリテラシー
1万人にインタビューした話し方のプロがコミュニケーションのポイントを発信
著者:柿崎元子フリーアナウンサー
テレビ東京、NHKでキャスターを務めたあと、通信社ブルームバーグで企業経営者を中心にのべ1万人にインタビューした実績を持つ。また30年のアナウンサーの経験から、人によって話し方の苦手意識にはある種の法則があることを発見し、伝え方に悩む人向けにパーソナルレッスンやコンサルティングを行なっている。ニッポン放送では週1のニュースデスクを担当。明治学院大学社会学部講師、東京工芸大学芸術学部講師。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修士
Facebookページ @Announce.AUBE





