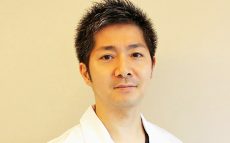南極「昭和基地」に、調理隊員が「こっそり埋めた思い出の品」とは
公開: 更新:
それぞれの朝は、それぞれの物語を連れてやってきます。

観測船「ふじ」(手前)3代目「しらせ」
新宿区新宿1丁目……新宿御苑が近く飲食店が多いこのエリアに、「八十八(やそはち)」という居酒屋さんがあります。お店を営むのは、中村喜昭さん・66歳。奥様が沖縄出身ということで、泡盛と沖縄料理が楽しめるお店です。
中村さんは、群馬県沼田市の出身。いわゆる「金の卵」の最後の世代で、中学を卒業すると夜行列車に揺られて上野駅へ。就職したのは、半蔵門にある結婚式場・東條會館でした。
「いまは写真館が残っていますが、当時は結婚式場が有名でしたね。フランス料理の調理師に採用されて、初めのうちは鍋洗いと玉ねぎの皮剥き。包丁が持てるようになったら、キャベツの千切りでした」

昭和基地にて 22歳の中村さん
21歳のころ、まかない料理がつくれるようになると、職場の先輩からこう言われます。
「おい中村! 一度は南極に行った方がいいぞ。給料が倍もらえるからな」
東條會館では、若い調理師が南極観測隊の調理隊員として、代々派遣されていました。
中村さんは背が高くガタイがいいので、中学生のころは「番長」と呼ばれていたそうです。南極行きが決まり、新聞に記事が載ると「あの番長が南極に行くってよ!」と、地元では大騒ぎになりました。
日の丸を背負って南極へ。中村さんは「故郷へ錦を飾った」と誇らしい気持ちで、観測船「ふじ」に乗り込みました。「第21次南極地域観測隊」の一員として晴海埠頭を出港したのは、1979年11月21日のことでした。

東條會館でフランス料理を手掛けていたころの中村さん
太平洋を南下する観測船「ふじ」。氷を砕く砕氷船は意外にも波に弱く、ちょっと海が荒れただけでも大揺れになったそうです。ひどい船酔いに苦しみながら、2ヵ月かけて南極の昭和基地に到着。こうして「21次越冬隊」33名による、1年間の任務が始まりました。
昭和基地で中村さんは、朝昼晩の料理を担当。研究者、エンジニア、通信士、医者など、33人の隊員は日本各地から集まっているので、好みの味が全く違います。味噌汁は鍋を2つ用意し、白味噌と赤味噌を分けてつくるほどです。
隊員に人気なのは天ぷらだったそうです。しかし、自慢の天つゆを用意した中村さんは、隊員の食べ方に驚いたことがありました。
「揚げたての天ぷらに、ドバドバとソースをかけているんです。『ちょっと、天つゆで食べてよ。こっちの方が美味しいから』と言っても、『九州じゃ天ぷらはソースで食うんだ』と聞かないんですよ」
隊員のなかで最年少だった中村さんは、「あれを手伝ってくれ」「これを手伝ってくれ」と頼まれ、分解して運んできたセスナ機の組み立ても手伝ったそうです。

いまはとても優しい元番長の中村さん
6月に入ると、南極は冬を迎えます。
「最もつらかったのは真冬の時期でしたね。マイナス60度も経験しましたが、寒さよりつらかったのは太陽が出ないこと。1日真っ暗なんです。あれには気が滅入ったなぁ」
みんなで酒を飲んでいると、些細なことでギスギスすることもありました。そんな夜、館内放送で「本日もオーロラが暴れております!」と流れると、すぐにウイスキーのボトルを持ち、オーロラ見物に出かけたそうです。
マイナス20度~30度のなか、マグカップに南極の氷を突っ込んでウイスキーを注ぐと、「プチプチ」と氷のなかの気泡が弾け、オンザロックがハイボールのような飲み心地になるのだとか。「この気泡は3万年~4万年前の空気だよ」と研究者から聞いて、中村さんは隊員とぎくしゃくしていたことがバカらしくなりました。

いまでは持ち出すことができない南極の石
南極に春が訪れると、33人の隊員たちは家族や兄弟のような仲になっていました。味噌汁も合わせ味噌にして、1つの鍋でつくるようになります。そして1年が経つと、観測船「ふじ」がやって来ます。隊員へ出す料理も終わりだと思うと、中村さんは寂しさが込み上げてきました。
「南極に思い出を残したい」と思った中村さんは、観測船の甲板で撮った写真や、隊員の名刺、東京からの電報などを小さな鍋に入れ、タイムカプセルにして調理場の裏にこっそり埋めました。
「いつか掘り起こしに、南極へ行きたい」
いまも「番長」の雰囲気を漂わせる中村さんは、あの日の思い出を、お店のお客さんに語り続けています。

旬菜厨房「八十八」は新宿御苑から徒歩3分
■旬菜厨房「八十八(やそはち)」
住所:新宿区新宿1-29-7 新宿ウィステリアビルB1
(東京メトロ丸ノ内線の新宿御苑前駅2番出口を出て徒歩3分)
営業時間:月~土、祝前日 17:30~翌0:00(料理L.O. 22:30)
定休日:日・祝日