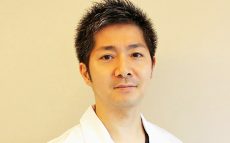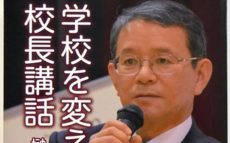それぞれの朝は、それぞれの物語を連れてやってきます。

1960年代のラジオ
東京・新宿から中央線の特急「あずさ」でおよそ2時間半の信州・松本。この町に、ラジオの受信機を集めた「日本ラジオ博物館」があります。
館長の岡部匡伸さんは、1964年生まれの58歳。東京で機械いじりが大好きなご家族とともに育ち、現在は横浜市内にお住まいです。現役の会社員としてお勤めの傍ら、月に数回、博物館のある松本へ通っています。
「日本ラジオ博物館」の館内には、骨董品のラジオ(約200点)がズラリ! 岡部さん自身も、ご自宅でさまざまなお宝のラジオに囲まれながら暮らしています。
岡部さんは青春時代、さまざまな放送局のラジオ番組を聴いて、局に受信報告書を送り、いわゆる「ベリカード」を集めることに熱中していました。相棒は、ご近所の大掃除をきっかけに譲り受けた真空管のラジオ。機械の調子が悪いときは、自分で修理しながら大事に使っていました。
進学した工業高校の文化祭では、ラジオ好きが高じて「放送博物館」をモチーフにした展示を行ったことをきっかけに、「ラジオの受信機」の収集熱に火が点きます。大学時代はアンティークショップのアルバイトを通して、ラジオだけでなく、テレビやオーディオにも触手を伸ばし、その数はどんどん増えていきました。

日本ラジオ博物館・岡部匡伸館長 1940年代のラジオとともに
社会人になってからは骨董品市にも足しげく通い、気が付くと、自宅が集めたお宝で溢れかえってしまいました。
「いちばん好きなラジオに絞って、あとは手放すことにしよう」
お宝の買い手がだんだんと付いていくなか、岡部さんに声をかけてくる人も現れました。
「よかったら古い家だけれど、うちの空いている建物に、岡部さんのお宝を置きませんか?」
保管場所の提供を申し出てくれたのは、信州・松本在住の方でした。
岡部さんのお宝をミュージアムとして展示する形で、いまから10年前の2012年5月、国宝・松本城からほど近い場所にあった昔の古い蔵を使って、「日本ラジオ博物館」は開館しました。松本市はたまたま、町じゅうを「博物館」に見立てる町づくりを行っていたことも、開館の追い風となりました。

AM・FM・短波を聴くことができるラジオ
岡部さんはこの10年を振り返って、博物館のお客様には「2つのタイプ」がいると分析しています。1つは、お城などの観光のついでに寄ってくれるお客様。もう1つは、何らかの形で「ラジオ」に関わっていた年配の方や、そのご家族の方。
実際、昔の音響機器メーカー創業者のご子息が訪問してくださったことから、展示が充実した側面もあり、本当に多くの人がラジオに関わっていると感じています。
「日本ラジオ博物館」では、今年(2022年)3月から「ラジオのはじまり」という企画展を始めました。最も力を入れたのは、「ラジオが生まれる前」のお話。19世紀の終わり、「電波」の存在が実験で明らかになり、火花を使って電波を送る送信機から、いわゆる「鉱石ラジオ」の原理を使った受信機などができていきました。
そのなかで真空管が開発され、日露戦争の日本海海戦やタイタニック号の遭難などを教訓としながら、無線技術が発達していきました。さらに第一次世界大戦の終結後は、余った軍用品を民間が使えるようになったことで、高音質の音を届けられるようになります。
そして1920年、アメリカで世界初の商業用ラジオの誕生に至りました。

いまからおよそ100年前のラジオ
2年前の2020年は、ラジオ誕生100年というメモリアルな1年でした。しかし、コロナ禍のためにお祝いムードすら自粛となってしまったのが、岡部さんは残念で仕方ありませんでした。そこで、開館10周年の今年に合わせ、企画展を開いたというわけです。
「なぜラジオが聴こえるのかということを、もっと多くの方に知って欲しいんです」
およそ100年分のラジオを前に、岡部さんは熱く語ります。それというのも、開館にあたって海外の放送関係の博物館を巡ったとき、世界ではアマチュア無線をはじめとした「ラジオの前身をつくった人たち」への尊敬の気持ちが大きいことに、感銘を受けたからです。
一方、岡部さんには悩みもあります。2007年登場のスマートフォン、「iPhone 3G」を展示するかどうか。実はそれ以来15年間、ラジオを聴くための新しい技術は商品化されていません。スマホが「最後の展示物」になってしまうのではないかと、不安も抱いているのです。
「でも、ラジオの文化を次の世代につなぎたいんです!」
岡部さんのラジオ愛は、ソフトにもハードにも満ち溢れています。