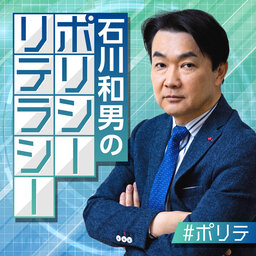政策アナリストの石川和男がパーソナリティを務めるニッポン放送Podcast番組「石川和男のエネルギーリテラシー」に、東京大学大学院情報学環・開沼博准教授がゲスト出演。福島第一原発事故の除染作業で出た土、いわゆる「除染土壌」について「科学的には98~99%くらいのイメージで再利用できる」と指摘した。
福島第一原発事故の除染作業で出た土、いわゆる「除染土壌」。帰還困難区域外の除染土壌の中間貯蔵施設への搬入は昨年完了し、その量は東京ドーム約11杯分に及んでいる。政府は法律に基づき、これらの除染土壌のうち放射能濃度が1kgあたり8,000ベクレル以下の土壌を再生利用、残りは2045年3月までに県外で最終処分するとしている。
開沼氏は除染土壌の定義などを詳しく説明した上で「全部が安全、全部が危険という話ではありません。ごみや産業廃棄物も同じですが、危険なものとそうでないものに分けていって、危険じゃないものは再利用、リサイクルしていく」と述べ、中間貯蔵施設に集められた土のうち「4分の3くらいが危険じゃない」と指摘。「そこの横で1年間、作業をしたと仮定して、ふつうに生きているよりも年間1ミリシーベルト被ばくが追加される」程度だとし、「何なら全裸で立って、全部放射線受けますっていう状態で1年間過ごしたとしても問題ない」と語った。開沼氏によると、ふつうに日常生活を送っているだけで年間2.1ミリシーベルト、病院の検査などでCTスキャンを受けると5~15ミリシーベルトの被ばく量があるという。
また、残る4分の1について開沼氏は「今の時点で4分の1が危ない。これを減容化、さらに減らすことができる。この4分の1の中で、線量が高いものと低いものにさらに選り分けるような技術開発が進んでいます。となると、実は(4分の1の)9割以上は4分の3側に分けられる。科学的には(除染土壌全体の)98~99%くらいは再利用できる」と言及した。