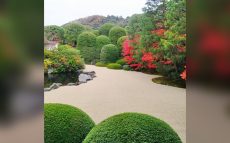「エスカレーター」という名称「使えなかった時期」 何があった?
公開: 更新:
あなたの朝がいつもイイ朝でありますように---ニッポン放送『羽田美智子のいってらっしゃい』。3月4日放送分のテーマは「エスカレーター」です。

※画像はイメージです
「エスカレーター」という名前が初めて登場したのは1859年です。名前の由来は、ラテン語で「階段」を意味する「スカラ(Scala)」と「エレベーター」を組み合わせたと考えられています。
ところが「エスカレーター」という名前は、アメリカの「オーチス・エレベーター社」が商標登録したため、しばらく使うことができなかったそうです。そのため日本では「自動階段」「移動式階段」などの名前で呼ばれていました。1950年になると、ようやく「エスカレーター」は一般名称として使われるようになります。
エスカレーターの人が乗る部分は「踏段(ふみだん)」と言います。踏段の幅によって、1段につき乗れる人数は「2人まで」、または「1人まで」と決められているそうです。
それ以上の人数、例えば3人で乗ろうとした場合、真ん中の人は手すりをつかむことができません。エスカレーターでは手すりをつかんで乗る状態が「安全で正しい乗り方」とされているため、安全面から3人以上は乗ることができないそうです。