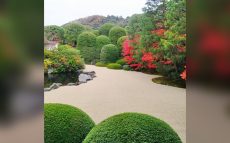「蒲焼き」の「蒲」ってどんな意味?
公開: 更新:
あなたの朝がいつもイイ朝でありますように---ニッポン放送『羽田美智子のいってらっしゃい』。7月27日放送分のテーマは「ウナギの雑学」です。

※画像はイメージです
ウナギの調理法のひとつに「蒲焼き」があります。ウナギやアナゴ、ハモ、イワシなどを開いて骨を取り、醤油やみりんなどでつくったタレをつけながら焼く料理です。
「蒲焼き」という名前の由来は諸説ありますが、昔はウナギを開かず、竹の串に刺して丸焼きにしていたそうです。その形が「蒲」という水草の穂の部分(蒲の穂)に似ていることから「がまやき」と呼ばれ、それが「蒲焼き」に変化したと言われています。
そして、江戸時代には「ウナギの蒲焼き」が本格的に知れ渡っていきます。
また、ウナギの開き方について関東は「背開き」、関西は「腹開き」と言われています。江戸時代、関東では武士の文化で「お腹を開くのは切腹をイメージさせ、縁起が悪い」と嫌われており、背中から開くようになったと考えられています。
それに対し、関西は商人文化で「お客さんとは腹を割って話せるように」と、お腹から包丁を入れていたそうです。
さらに関東では、一度焼く「白焼き」を行ってから蒸したものをタレにつけて焼きますが、関西では蒸さずに直火で焼きます。関東でウナギを蒸すのは、江戸っ子はせっかちで気が短いため、「注文を受けてから少しでも早く出せるように」という意図があったようです。