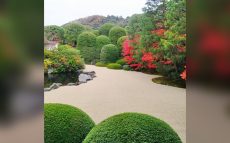世界で「ウナギ」はどう食べる? 燻製やアヒージョにする国も
公開: 更新:
あなたの朝がいつもイイ朝でありますように---ニッポン放送『羽田美智子のいってらっしゃい』。7月28日放送分のテーマは「ウナギの雑学」です。

※画像はイメージです
季節の移り変わりを表わす言葉の1つに「土用」があります。「土用」は春・夏・秋・冬それぞれにありますが、なかでも「夏の土用の丑の日」にはウナギを食べる風習があります。
理由は諸説ありますが、例えば「夏バテを防ぐため」というもの。ウナギには、目や皮膚の粘膜を健康に保ったり、抵抗力を強めたりする働きがある「ビタミンA」が豊富に含まれています。
他にも「ビタミンB1、B2、E、D」「カルシウム」「鉄分」「亜鉛」。人間の体に欠かせない必須脂肪酸の1つである「DHA」や「EPA」。また「コラーゲン」など、夏バテ予防に必要な栄養素が豊富に含まれています。
ウナギを食べる文化は日本だけでなく、外国にもあります。日本では「蒲焼き」が一般的ですが、例えばヨーロッパでは「ウナギの燻製」がポピュラーだそうです。そのままパンに乗せたり、サンドイッチにして食べられています。
他にも、フランスではウナギをワインで煮込んだり、スペインではウナギの稚魚「シラスウナギ」をアヒージョにしたりするそうです。