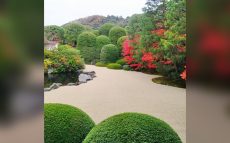昔は「水筒」の代わりに何を使っていたの?
公開: 更新:
あなたの朝がいつもイイ朝でありますように---ニッポン放送『羽田美智子のいってらっしゃい』。5月22日放送分のテーマは「水筒」です。

※画像はイメージです
水は私たち人間を始め、この地球で生活する生き物たちにとって必要不可欠なものです。すべての生命を支える、まさに「命の水」です。
はるか昔から人々は、水をたくわえておくための道具や器をつくり出してきました。なかでも水を運び、飲む道具として発展したのが「水筒」です。
水筒の歴史はとても古いと言われています。紀元前3000年ごろ、中国やヨーロッパでは加工した動物の皮を縫い合わせ、袋状にしたものに水を入れて持ち歩いていたそうです。
一方、天然の容器として重宝されたのが、ウリ科の植物である「ひょうたん」です。ひょうたんの実は独特のユニークな形をしていますが、中身を取り除いて乾燥させたものを、水を入れる容器として使っていたそうです。
ひょうたんは熱帯アフリカが原産と言われていますが、古くから世界各地に存在しており、日本にも縄文時代の初めには伝わっていたそうです。
また当時、東アジアでよく利用されていたのが「竹筒」で、日本でも使われるようになりました。特に日本の竹は小ぶりであり、持ち運びにちょうどよく、水筒として最適だったそうです。