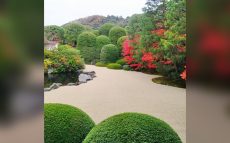平安時代の「かき氷」には、何がかけられていたの?
公開: 更新:
あなたの朝がいつもイイ朝でありますように---ニッポン放送『羽田美智子のいってらっしゃい』。7月10日放送分のテーマは「かき氷」です。

※画像はイメージです
いまでこそ「かき氷」は季節に関係なく、1年中食べることができますが、古くから夏の風物詩とされていました。紀元前の時代から、氷は食べ物の保存用として、あるいは食用として利用されてきたそうです。
平安時代に清少納言が書いた随筆『枕草子』には、かき氷とされるものが登場しています。「あてなるもの(上品なもの)」として、「削った氷に甘葛(あまづら)と呼ばれる、植物からつくられた甘味料をかけたもの」を挙げているそうです。
当時は冬になると山などから天然の氷を運んできて、「氷室」と呼ばれる場所に保管していました。その氷は、夏になると都まで運ばれ、とても貴重なものとして扱われていました。
また、当時は甘葛やハチミツ、水あめなどの甘味料は高貴な身分の人しか口にすることができない、貴重な食材でした。そのため、「削った氷に甘味料をかけたもの」は貴族のなかでも限られた人間だけしか食べられず、まさに「あてなるもの」だったそうです。