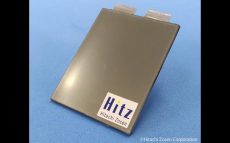押し寄せる軽自動車電動化の波
公開: 更新:
「報道部畑中デスクの独り言」(第260回)
ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム。今回は、軽自動車の電動化について---

画像を見る(全9枚) 日産の電動軽自動車コンセプトカー「IMk」 市販車ではどのような形になるのか?
お盆休みが終わりました。自動車業界はかつてこの時期になると、「秋の商戦」と称して、新型車を一斉に発表していました。
週末の新聞は「新型○○発表会」というメーカー、ディーラーの広告で埋め尽くされたものですが、そんな熱い時代もいまは昔。しかし、そうした広告はなくとも、クルマのトレンドというものはいまも存在します。
自動車各社は7月~8月にかけて、2021年第1四半期の決算を発表しました。新型コロナウイルス感染拡大、半導体供給不足や原材料価格高騰の問題は依然残るものの、昨年(2020年)の状況からは底を打ち、回復基調に転じています。
「日産は確実にその輝きを取り戻しつつある。これまでは自分自身との戦い。これから本当の意味で日産という会社の真価が問われる」
回復が遅れていた日産自動車の2022年度通期業績予想は、連結最終損益600億円の黒字に上方修正されました。
通期としては3年ぶりの黒字。オンラインの決算会見で姿を見せた内田誠社長の表情は、心なしか弾んでいたように感じました。「ニッサンネクスト」と呼ばれる構造改革が進み、北米市場が持ち直していることをその理由としています。
一方、こうした業績発表とは別に、7月~8月にかけていくつかの動きがありました。共通のキーワードは「軽自動車の電動化」です。
日産の決算発表でも今後の電動化戦略について言及があり、軽自動車のEV=電気自動車を2022年初頭に日本国内に投入する予定が明かされました。これについては共同開発している三菱自動車も「2022年度前半に出すつもり」(長岡宏代表執行役)としており、歩調を合わせています。
軽のEV化においては、ホンダが2024年に、スズキは2025年に市場に投入する考えを示していますが、日産・三菱連合が一歩先んじる形です。三菱自動車はアイ・ミーブ、ミニキャブで実績があり、パイオニアとしての自信をにじませていました。
軽の電動化には別のアプローチもありました。商用車の分野でスズキとダイハツが、トヨタ自動車を核にした連合への参加を発表。トヨタはトラックの分野でいすゞ自動車と日野自動車との提携を結んでいますが、これを軽自動車にも広げた形、いわば、プラットフォーム側からの「仲間づくり」です。
電動化において、単独では体力的に厳しい軽自動車2社に対し、トヨタが技術を供与することによって解決を図るという意義もあります。
軽は商用車の分野でも存在感を示しています。2019年、軽自動車は191万台余りを販売しましたが、そのなかで軽商用車は43万台余り、ほぼ5台に1台を占めています。軽のトラックは農道をはじめとするさまざまな仕事場で重宝されています。本格的な電動化を、まずは商用車の分野から始めて行こうということのようです。
「軽自動車は日本の道がつくった国民車」
提携会見でトヨタの豊田章男社長はこのように語りました。軽自動車を自社生産していないトヨタがここまでの取り組みを見せるのは、それだけ、日本の自動車産業にとって次世代のカギを握ると認識していることに他なりません。
軽自動車は私もときどき乗ることがありますが、必要にして十分な走行性能、狭い道で小回りが効き、視界もよく、痒いところに手が届くような収納スペースが豊富。エアコンやカーナビも普通に装備されており、一般道を走る限りは「これ以上何が必要だろう」と思えます。日本に合ったクルマだなと実感します。
それだけに軽自動車の電動化は、こういった「日本人の足」にどのような影響を与えるのか、大変に興味深いところです。バッテリーのコストが劇的に下がらない限り、価格上昇は避けられません。
売りである「安さ」をどう維持して行くのか。そして、バッテリー搭載によって増える重量にどう対処するのか。ことによると全長3.4m、全幅1.48m、全高2.0m、排気量660cc以下、乗車定員4名以下という現状の規格にも影響を与えるかも知れません。
また、こんな動きもあります。中国では「宏光ミニ」という格安EVが出現しました。「軽自動車界の“黒船”になる」という声も出ており、三菱自動車の長岡執行役も「中国製のEVも脅威になる」と、軽自動車のライバルと認める発言をしています。
中国だけではありません。国内には「FOMM」というベンチャー企業があります。全長2.5mあまりと、軽自動車規格に適合しながら、よりコンパクトで4人が乗れ、緊急時には「水に浮く」電気自動車の量産を始めました。
FOMMの経営トップはスズキ出身、その後トヨタ系の車体会社を経て、2013年にこの企業を立ち上げます。電気自動車「FOMM ONE」はタイ製ではあるものの、粘り強く交渉を重ねて“日本車”として扱われ、環境省のイベントにも参加していました。こうした新興勢力が台頭するなかで、日本の軽自動車がどのように対処して行くのかも課題になります。
軽自動車の規格は、時代に応じて変遷を遂げて来ました。例えば排気量でみると、360cc→550cc→660ccに増加しています。しかし、規格そのものは維持されています。
居住性向上、衝突安全性能の強化と引き換えに、クルマの寸法がどんどん肥大化して行くなか、軽自動車はその時代の規格、限られた寸法のなかで最良の性能を追求して来ました。これをしてスズキの鈴木修前会長は「軽は芸術品」と表現したわけです。
私はこう考えます。限られた制約のなかで最大の努力をする……それは「道を究める」ことにも通じ、日本人の美徳の1つとさえ思います。「非関税障壁」「ガラ軽(軽のガラパゴス化)」と揶揄されても、軽自動車規格そのものは維持すべきものだと……。
一方、鈴木修前会長が会長退任前に語った「芸術品を守り続けて欲しい」という発言には、もう1つの意味があるように感じます。
軽自動車はこれまで厳しい競争、環境のなかで、いくつもの新たな発想のクルマが登場しました。古くは1958年に発売された「スバル360」、航空機技術により、量産型の軽自動車で初めて大人4人の乗車を可能にしました。
1979年に登場した「初代スズキ・アルト」はボンネットバンという商用車でシンプルに徹し、全国統一47万円という低価格で大ヒットしました。当時の鈴木修社長が「こんなの“あると”いい」の一言で発売にこぎつけたと言われています。
1993年に発売された「スズキ・ワゴンR」は、軽のハイトワゴンという新たなジャンルを確立しました。そして、1970年に初代が発売された「スズキ・ジムニー」は軽のオフロード4WDとして、2002年に初代が登場した「ダイハツ・コペン」は軽のオープンスポーツカーとして、軽ならではの存在感を放ち続けています。
「芸術品を守る」、それは限られた条件のなかで最良を目指すとともに、創造力、発想力を維持して行くことでもある……これからの時代を生き残るカギではないかと思います。(了)