東京都医師会・学校精神保健検討委員会委員長で「子どもと家族のメンタルクリニックやまねこ」院長の田中哲氏が2月25日、ニッポン放送「モーニングライフアップ 今日の早起きドクター」に出演。子どもの登校拒否と不登校において、親がするべきことについて解説した。

ニッポン放送「モーニングライフアップ 今日の早起きドクター」
どうすれば大人が子どもの心に寄り添うことができるのか
飯田浩司アナウンサー)子どもの登校拒否と不登校について、親がするべきことは何でしょうか?
田中)子どものすることには全部意味があるのです。その意味にたどり着かない限り、子どもの行動は変わりませんし、子ども自身も生きやすくなりません。「どうすれば大人が子どもの心に寄り添うことができるのか」というのが、対策の最も大事なところだと思います。
飯田)親からすると、自分の庇護下にもあるということで、ともすると「コントロール可能なのだ」とか「自分の子どもなのだから、他よりもよく見せたい」とか、持ち物のような感覚に陥りがちになるのです。自戒も込めてですが。
田中)親は学力や運動能力など、見えるところを磨こうとします。外見をブラッシュアップしようとするのですが、そういうものは本来、子どもの内側にあるものがにじみ出て表れて来るものです。
飯田)本来は。
田中)いまの時代は「どう見えるか」を磨くことに意識が先行してしまい、「子どもの気持ちがどのように成長して行くか」、「子どもはどんなことを感じているのだろうか」というところに目が行きにくくなっている気がします。
飯田)確かに「これを着なさい」、「これを食べなさい」、「これを勉強しなさい」。全部、指示している。
田中)そうですよね。指示していますよね。
子どもの選んだものを、「いいよね」と言ってあげられるかどうか
飯田)「何を食べたい?」と聞くこともあるのですが、うちの子どもも「何でもいい」と言うことが多いのです。これはシグナルとしてはどうですか?
田中)「どうせ何か言っても、親が食べさせたいものを食べさせられる」と思っているのです。
飯田)あまりよくない兆候だと思った方がいいですか?
田中)そこで「これとこれ、どっちがいい?」とか、「どうしたい?」と聞いてあげる。もし、食べ物や着るものなどで、親が「それはいかがなものか」と思うものを子どもがチョイスしても、「君らしくていいよね」と言ってあげられるかどうかなのです。
飯田)「いいよね」と言ってあげられるかどうか。
田中)「君らしい」ということを、子どもの表現として親が大事だと思ってあげられるかどうか。これを大事にできれば、親子関係も変わって来ると思います。
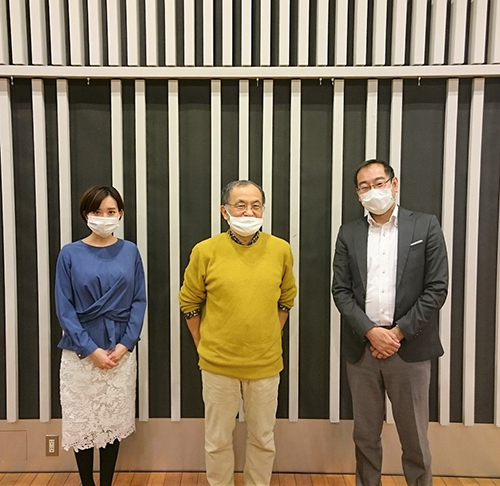
新行市佳アナウンサー、田中哲氏、飯田浩司アナウンサー
子どもがいつもと違うことをするのは、サインでもある ~それに反応しなければ諦めてしまう
飯田)引きこもり、あるいは不登校・登校拒否、いろいろな症状を見て来ていらっしゃると思います。何かきっかけや予兆を感じるところはありますか?
田中)「子どもがいつもと違うことを始めたな」と思ったときは、必ず理由があるのです。子どもはその糸口を出してくれていると思うのですよ。その糸口に大人がきちんと食いついて行けるのか、たどることができるかどうかを、子どもは逆に試しているのだと思います。全然反応しないと「これはダメだ」となって、気持ちを出さなくなってしまいます。
子どもに関わることを決してやめないでください
飯田)リスナーの皆さんに、改めて訴えたいことがありましたらお願いします。
田中)子どもは将来の私たちを支えてくれる大事な人たちです。次の時代を任せることができるような子どもを育てて行くのが、私たちの大きな使命だと思います。「決して、子どもに関わることをやめたり、手控えたりしないでいただきたい」というのがお願いです。
飯田)それは自分の子どもかどうかは関係ないということですね。
田中)そうです。






