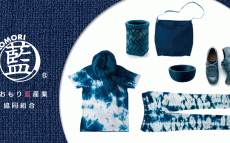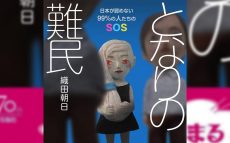それぞれの朝は、それぞれの物語を連れてやってきます。

NPO法人「こどもソーシャルワークセンター」の取り組み
突然の休校要請によって、長い春休みを過ごすことになった子どもたち。一部の学校は再開しているところもあるようですが、友だちと話せない、遊べない…その小さな胸のなかには、いかばかりのストレスが充満していることでしょうか。
それと同時に、頭をかかえている親御さんも多いことでしょう。たとえばひとり親の家庭では、子どもの面倒をどうやって見るのか? 親が病気療養中の家庭では、子どもの世話をどうするのか?
「こうした問題はいま、にわかにクローズアップされていますが、実は日本が普段から内包している問題なんです」
こう話すのは、滋賀県大津市のNPO法人「こどもソーシャルワークセンター」の代表、幸重忠孝さんです。大学を卒業すると同時に社会福祉士の資格を取った幸重さんは、現在46歳。最初の仕事は、児童養護施設の職員でした。

一斉休校で浮き彫りになっている問題は、「日本が普段から内包している問題」だという
たとえば、家庭での虐待や貧困によって「この子は家族とは暮らして行けない」と児童相談所が判断した、3歳~18歳までの子どもたちは、児童養護施設で暮らすことになります。幸重さんは言います。
「子どもたちはそれぞれ楽しく暮らしてくれていますが、他人との共同生活のなかで規則ができて、ある種の息苦しさが生まれます。また子どもは勉強や遊び、暮らしのなかで、かまってほしいという欲求を高めます。その全てに応えるのは、限られた人数の職員では難しい。そして18歳になった子は、『若いのだから頑張れるだろう』という無責任な期待を負わされて、児童養護施設を出なければなりません。こうした子どもたちはいま、4万5000人ほどいるんです」
施設の限界のようなものを感じた幸重さんは、大学で8年ほど教鞭を執り、30代半ばでスクールソーシャルワーカーの道へ進みます。文部科学省が「これからの日本の学校には必要なものだ」と認めた新しい仕組みでした。
「義務教育の学校というのは、実にいいところだと思います。誰でも平等に通えます。そして、子どもたちの異変をいち早く見つけることができる。いわば、子どもたちが安心・安全に暮らして行くための最前線なんです」と、幸重さんは言います。
ところが、学校は時間が来ると終わってしまう。家に帰れば、そこには相変わらずの厳しい現実が待っている。休みの日は致命的だと言います。

「『ほっ』とるーむ」「ジョブキャッチ」などさまざまな取り組みを実施している
学校にも限界があることが、次第に見えて来ました。自分の居場所をどこにも見つけることができずに、学校と家庭の間に落ちて行ってしまう子どもたちが少なくないと言います。
次に幸重さんが辿り着いたのは、京都で40年間ほど活動を続けている「山科醍醐こどものひろば」でした。そこでは、専業スタッフとボランティアが生き生きと働いていました。
家でも学校でもない、のびのびとした温かい空間。学校や家庭がかかえ込んでいる問題を、ここならフォローできる。手に負えない問題は福祉へ橋渡ししてやることもできる。
幸重さんは「山科醍醐こどものひろば」の理事長を拝命して、次々に子どもたちの暮らしを守るための、いろいろな取り組みを実現しています。
子どもの貧困対策事業として打ち出したのは、「夜の子どもの生活支援」。「通学合宿」では、宿泊可能な施設を活用。近隣の小学校と連携し、夜間に1人で過ごす小学生たちは、平日の夕方5時~翌朝の登校時まで、学生サポーターたちと過ごします。

「トワイライトステイ」など夕方~夜間での取り組みも
「トワイライトステイ」は商店街の空き店舗を活用して、小中学生たちが夕方5時~夜9時まで、学生サポーターとマンツーマンで過ごします。どちらのコースにも「晩ごはん」と「お風呂の時間」が設けられ、お風呂の時間には近所の銭湯まで出かけて、子どもたちとの距離を縮めます。
いま貧困状態にあるとされる日本の子どもは、6人に1人と言われています。NPO法人が取り組む問題としては大きすぎるような気もしますが、幸重さんはきっぱりと言います。
「たしかに私たちが関わる子どもの数は、知れています。けれどもこの問題は、どんな地域でも自分の身の回りで起きている身近な問題としてとらえて行かなければ、解決できないでしょう。ソーシャルワーカーのソーシャルとは『社会』。私たちが戦いを挑んでいる相手は、『社会』なのです」